公開日 /-create_datetime-/
事業者の節税には欠かせない知識、固定資産税の計算方法を解説
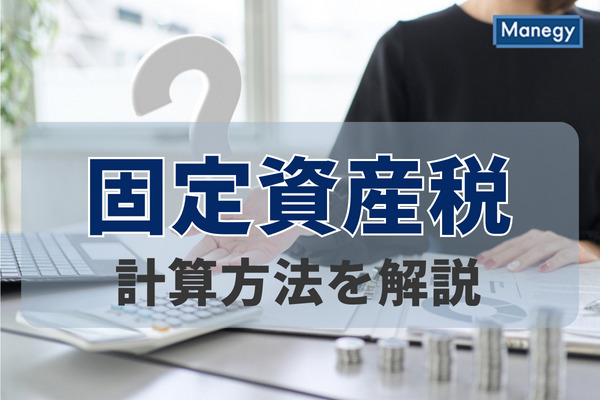
国税と地方税とを合わせると、日本にはおよそ50種類の税金があります。その中の一つである固定資産税は、個人のほか企業や個人事業主が所有する資産に課される直接税です。
事業を継続するためには、毎年固定資産税を納付する必要があり、経営者や経理担当者はその仕組みをよく理解しなければなりません。この記事ではビジネスの面から、固定資産税の計算方法を中心に解説します。
固定資産税の概要
固定資産税は個人と法人とを問わず、毎年1月1日の時点で所有する資産に対して課税される地方税の1種です。一括して固定資産税と呼ばれており、対象物は以下のように、「固定資産」と「償却資産」とに分類されます。
■関連ニュース
税の種類と歴史:「固定資産税」
固定資産に分類されるもの
土地、工場、事務所、営業所、店舗、倉庫など
償却資産に分類されるもの
事業者が所有する構築物(フェンス・看板など)、機械装置、工具器具備品など
これら2種類の課税対象については、各市町村が個別に決める「固定資産評価基準」をベースにして、それぞれに税額が計算されます。 固定資産に分類されるものは、市町村の固定資産課税台帳にもとづいて課税されます。償却資産に分類されるものは市町村に申告をしなければなりません。
固定資産税の計算方法①:固定資産の場合
固定資産税の計算方法は非常にシンプルで、以下の計算式で求められます。
固定資産税の金額 = 固定資産評価額(課税標準額)× 1.4%(標準税率)
簡単にいうと、各市町村の担当がそれぞれの土地や建物について調査し、それを固定資産評価基準と照合して固定資産評価額を決めます。その額に標準税率を掛けたものが固定資産税の金額になるのです。評価額は3年に1度見直しが行われます。
固定資産評価額の大まかな目安は、土地の場合は時価の約70%で、新築の建物の場合は50~60%と言われています。ただし、場所や構造などの条件により評価額は変わります。 また標準税率の1.4%も、市町村の条例により異なる税率を適用することが可能です。
固定資産税の計算方法②:償却資産の場合
償却資産に関しては、減価償却という考え方をもとに、会計上は一括ではなく分割して計上します。資産を取得した時点でまとめて経費にするのではなく、耐用年数に応じ分割して計上するのです。
そのため償却資産は、固定資産とは異なる方法で課税標準額を決めなければなりません。その計算式は、資産を取得した時期によって以下の2つに分けられます。
前年中に取得した償却資産の評価額 = 取得価額 ×(1 - 耐用年数に応ずる原価率÷2)
前年前に取得した償却資産の評価額 = 前年度評価額 ×(1 - 耐用年数に応ずる原価率)
この計算式のどちらかで求めた評価額をもとに、固定資産と同じ計算式を使って、以下のように償却資産の税額を算出します。
固定資産税(償却資産)の金額 = 評価額(課税標準額)× 1.4%(標準税率)
償却資産にはパソコンやコピー機などが含まれますが、ソフトウェアや特許権のような無形固定資産や、自動車税などの対象になるものには課税されません。
固定資産税の減免措置
固定資産税は、一つの市町村内で所有する資産の固定資産税を合計して、それぞれ以下の金額に満たない場合には納税が免除されます。
・土地などの固定資産税:~300,000円
・家屋などの固定資産税:~200,000円
・償却資産:~1,500,000円
ほかにも特例制度があり、たとえば中小企業が「先端設備等導入計画」の認定を受ければ、固定資産税の軽減などの特例を受けることが可能です。 最近では、新型コロナウイルスにより収入が減少した場合や、災害に遭った場合などにも特例措置が実施されています。
また状況に応じて、さまざまな特例や支援措置により、固定資産税の減免が認められる可能性があるため、一度、管轄の市町村に相談することをおすすめします。
固定資産税の納付方法
固定資産税は、毎年1月1日時点で所有している資産に課税されます。償却資産に関しては、1月31日までに「償却資産申告書」を市町村に提出しなければなりません。
納付額が決まったら、通常は4月上旬に市町村から納付書が送られてきます。全額を一括で納付するか、4月末、7月末、12月末、翌年2月末の4回に分けて納付します。 納付方法は現金のほか、口座振替やクレジットカード払いも可能です。ただし、納付期限を過ぎると延滞金が科される場合があるので注意しましょう。
まとめ
所有する資産が多くなると、固定資産税の負担が増える可能性があります。税負担を上手に緩和するためにも、経営者や経理担当者は、固定資産税の分類と計算方法を正しく把握しておかなければなりません。
とくに償却資産を経費として適切に計上することは、最終的には節税にもつながる可能性があります。また、固定資産税の減免制度を活用すれば、経営への負担を軽減できるかもしれません。日本の税制は複雑ですが、事業を発展させるためにも基本的な知識は身につけておきましょう。
※本記事の内容を参考にする際は、念のため専門家や関連省庁にご確認ください
■併せて読みたい関連ニュース
生前贈与の税制簡素化に向けた検討が開始。贈与税の何がどう変わるのかを詳しく解説
税について聞く、見る、話す、全国規模で開催される「税を考える週間」とは?
消費税の納付税額または還付税額の経理処理 2つの方式を解説
■参考サイト
総務省|固定資産税
中小企業庁|先端設備等導入計画について
※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。
おすすめコンテンツ
新着おすすめセミナー
人気記事ランキング
キャリア記事ランキング
新着動画
関連情報
-

健康経営の第一歩! 健診受診率100%を達成するコツ一覧
おすすめ資料 -

管理部門職種別 面接質問集【MS-Japan】
おすすめ資料 -

ハイブリッドワーク・ フリーアドレス導入に際して発生する課題は?
おすすめ資料 -

法人税対策・実物資産投資の新たな選択肢 最新情報掲載 『日本型オペレーティングリースガイドブック』
おすすめ資料 -

経理業務におけるスキャン代行活用事例
おすすめ資料 -

2026年1月施行「取適法」法改正に伴う「対応が必要な契約」を即座に把握できる人はわずか1割
ニュース -

売上1千億円を目指す企業で「半歩先を見据え、変化を楽しむ管理部門」の魅力【CFOインタビュー SmartHR 取締役CFO 森 雄志氏】
ニュース -

お金の流れと損益が一致しない『減価償却費』を理解しよう
ニュース -

国内転勤者に一律50万円支給で心理的負担を軽減 住友重機械工業のキャリア形成サポート
ニュース -

理想的な組織文化ってあるの?/リーダーのためのお役立ち道の文化づくり実践ガイド【第2話】
ニュース -

契約不適合責任とは?売買契約書で 注意すべきポイントについて
おすすめ資料 -

雇用契約書の記載事項を知りたい方必見!必須事項や注意点を解説
おすすめ資料 -

採用コンサルティング・ 採用業務代行 (RPO) サービス
おすすめ資料 -

26卒エンジニア学生551名に聞く|志望度が上がる・下がるサマーインターンシップ調査レポート
おすすめ資料 -

弁護士業におけるスキャン代行活用事例
おすすめ資料 -

「アサーティブコミュニケーション」の重要性と実践に向けた具体的な手法を学ぶ
ニュース -

労働保険料の勘定科目を完全解説|仕訳処理と経費計上の正しい考え方
ニュース -

上場企業も暗号資産で一攫千金?投資事業への参入相次ぐ
ニュース -

労働基準法の知られざる機能ーマズローの【欲求】とジラールの【欲望】から読み解く
ニュース -

クラウドストレージはバックアップになる?ランサムウェアとDR対策
ニュース



































