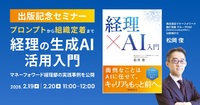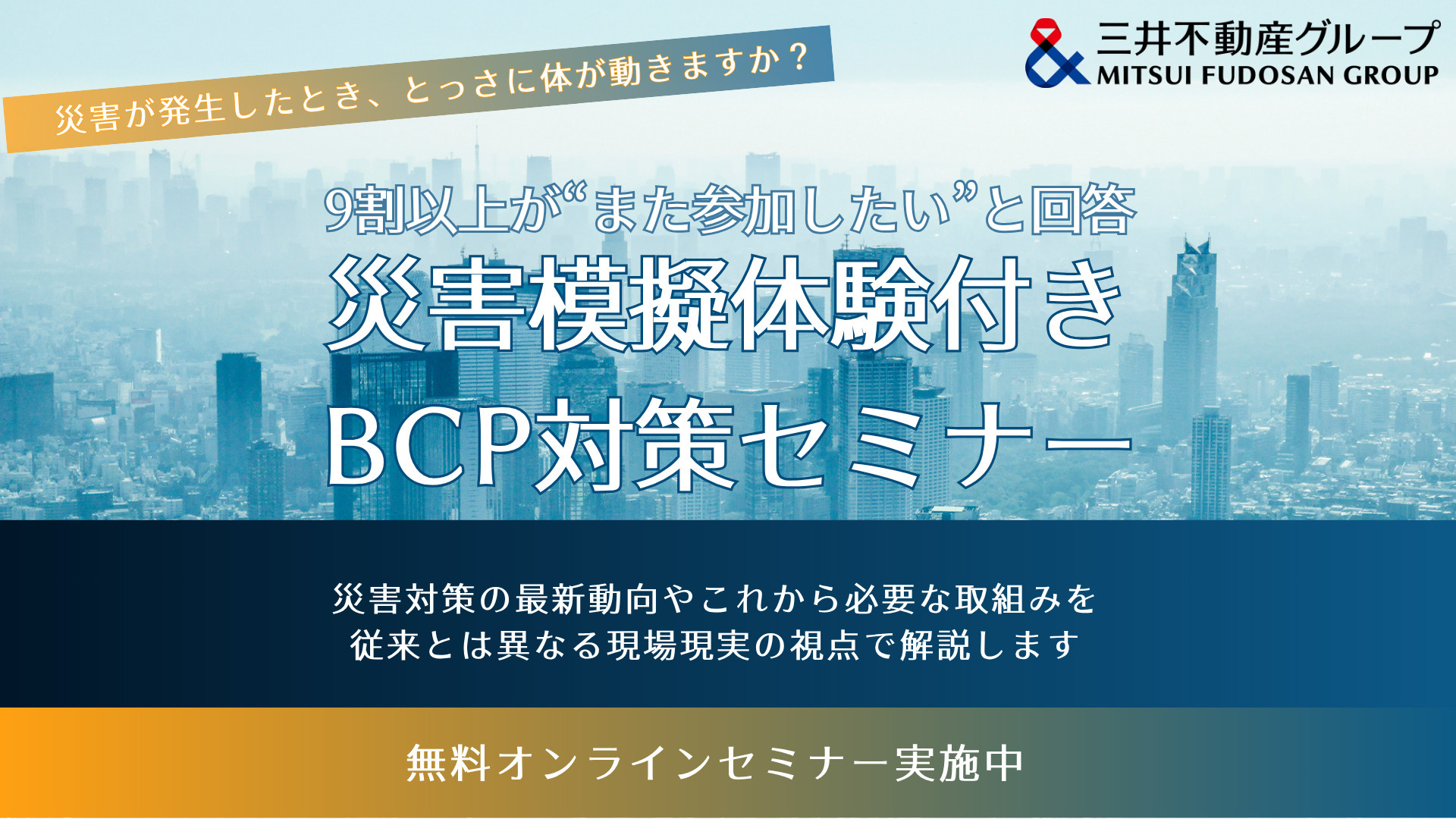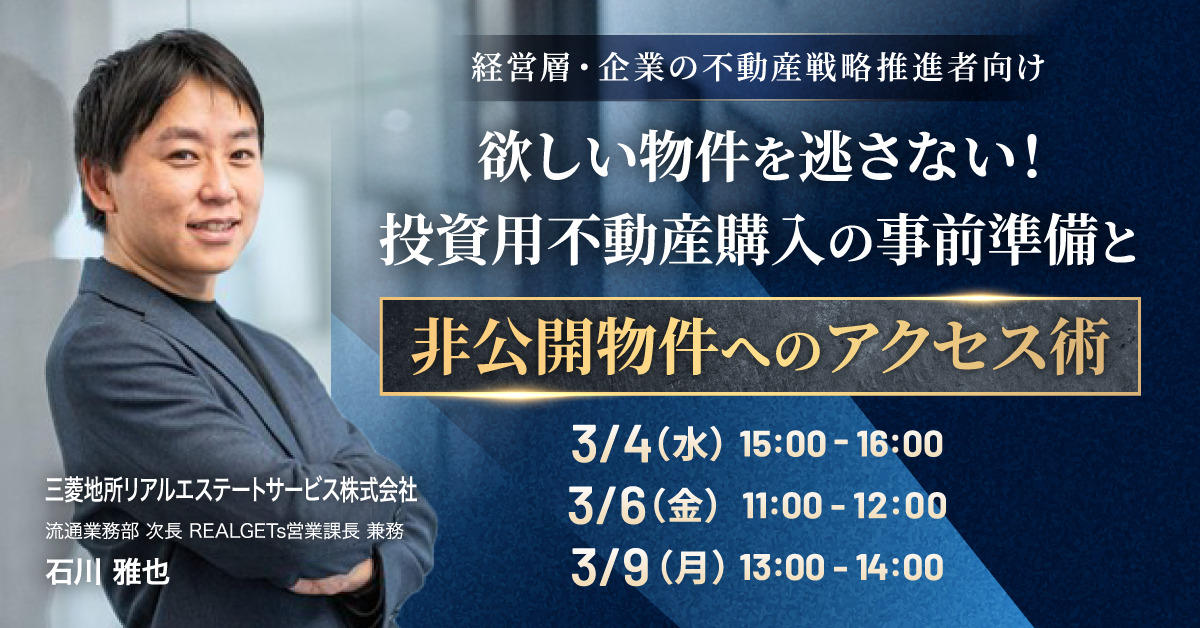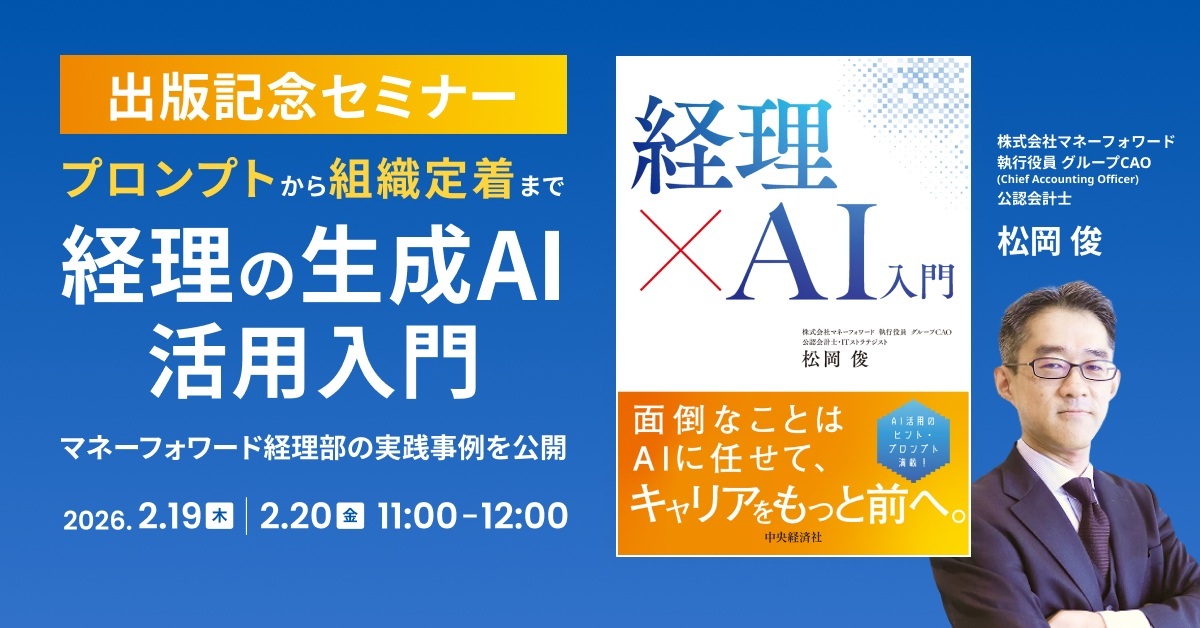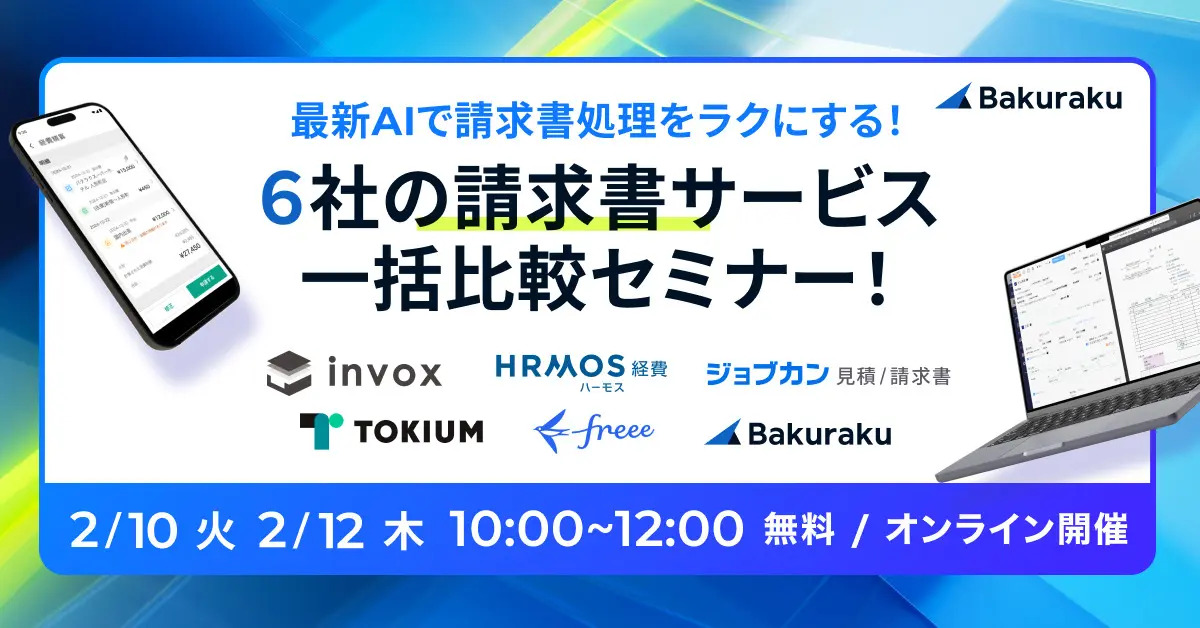公開日 /-create_datetime-/
副業は住民税でバレる?バレない方法はあるの?
副業に関心を持っている人が増えている昨今、多くの人が「副業を始めたいけど、会社にバレてしまうのではないか?」と悩んでいるかもしれません。しかし、副業をすること自体は法律的に問題ありません。本記事では、副業による住民税の申告や会社へのバレるリスク、さらにはバレない(バレにくい)方法について解説しています。ぜひ参考にしてください。
副業禁止の会社の場合は原則副業をしない方がよい
副業すること自体は法律的に問題なく、個人の判断で行うことはできます。政府は副業を促進していますが、依然副業禁止の会社も多く存在しているのが現実です。
副業禁止の会社に所属していて、仮に副業がバレてしまった場合、最悪退職処分となってしまうこともあるため、かなりハイリスクになってしまいます。そのため副業を禁止している会社では原則副業をしないという判断がベストです。
副業が会社にバレてしまう原因は住民税にある?
副業によって住民税でバレてしまう理由は、住民税の納税義務に関する法律にもとづいているためです。住民税は、市区町村に住民として在住している者が課税される税金であり、個人事業主やフリーランスなどの場合、収入に応じて課税されます。
具体的には、副業で得た収入が一定の金額以上(年間所得20万円以上)ある場合、住民税の申告が必要です。住民税の申告は、個人で行う場合(普通徴収)と源泉徴収制度を利用する場合(特別徴収)があります。
源泉徴収制度を利用する場合は、副業先からの給与から住民税を天引きされるため、住民税の申告が不要になりますが、勤務先に副業をしていることがバレる可能性があります。
つまり、住民税に関する申告や納税の手続きを適切に行わないと、副業がバレる可能性が高まってしまうのです。
副業が会社にバレない方法
①会社の同僚に副業をしていることを話さない
会社の同僚についポロリと副業をやっていることを話してしまう方がいますが、絶対に控えるようにしましょう。信頼している同僚とはいえ、不意に社内の人間に対して情報を漏らしてしまうことがあるかもしれません。
②住民税を普通徴収にする
住民税には特別徴収と普通徴収の二つの納税方法があります。
特別徴収は毎月の給料から住民税が天引きされる納税方法のことです。確定申告や住民税の申告書を記入する際、住民税の支払い方法を特別徴収にすると、本業の勤務先に住民税の情報が届いてしまってそのタイミングでバレてしまうことがあります。
ただし、住民税を給料からの天引きではなく自分で納付する納税方法の普通徴収を選択すると、副業に関わる住民税の情報が本業の勤務先ではなく自宅に届きます。そのため普通徴収の場合は副業がバレにくくなるでしょう。
③会社の競業他社や取引先で副業をしない
会社の競業他社や取引先で副業をする場合、副業がバレる可能性が高くなるかもしれません。
とくに、取引先で副業をする場合は、会社に対して忠誠心を欠いていると見られることがあるため、会社側から不信感を抱かれることがあります。
また、競業他社で副業をする場合は、会社の業務と関連する情報や技術を競業他社に漏らすことがないように注意する必要があります。競業秘密を守ることは、法的にも重要な義務です。
④アルバイトやパートは控える
アルバイトやパートの場合は「給与支払報告書」を市区町村に提出が必要です。それによって住民税が確定し、本業の勤務先に通知が行き、そのタイミングでバレてしまいます。要するに給与所得の場合は副業がバレてしまう可能性が高くなるのです。
一方で、Webライターやアフィリエイトなどの給与所得ではなく事業所得や雑所得の場合は、住民税を自分で申請し、自分で納付する普通徴収を選択できます。本業の勤務先に通知が行くこともないので、バレる可能性が低いでしょう。
副業の所得が20万円以下の場合は確定申告不要
年間の副業収入が20万円以下であった場合、確定申告は不要です。所得は「収入」から商品の仕入れや取引先との交際費などの「必要経費」を差し引いた金額を指します。
たとえばWebライターの報酬が30万円の場合、必要経費が0円の場合は確定申告が必要です。
しかし、せどり(転売)で収入が30万円で、必要経費にあたる商品調達費が15万円かかった場合、所得は15万円になるので確定申告は不要になります。
また、自宅を事務所や作業場として使用している場合、家賃や水道光熱費は一部経費に計上することが可能です。ただし自宅はプライベート空間としても利用しているため、すべてを経費には回せませ。
家賃や水道光熱費といった「家事関連費」を仕事用とプライベート用に分けることを「家事按分」と呼び、家賃であれば床面積、水道光熱費であれば使用時間などを考慮し、合理的に按分しなければなりません。
まとめ
副業収入が本業の勤務先にバレない方法について解説してきました。原則として副業禁止の会社での副業はおすすめできません。
まずは勤務先の就業規則を確認し、副業を始めたい方は参考にしてみてください。
■参考サイト
フリーランスの働き方、副業も含めた実態と問題点を分析
2023年副業実態調査 副業や兼業をする社会人は4年で2倍に!今後ますます働き方は変わる!?
※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。
おすすめコンテンツ
新着おすすめセミナー
人気記事ランキング
キャリア記事ランキング
新着動画
関連情報
-

上場企業・IPO準備企業必見!! 内部統制・監査の妨げになるアナログな入金消込とは
おすすめ資料 -

業務委託契約書の書き方のポイントは?知っておくべき基礎知識
おすすめ資料 -

ハイブリッドワーク・ フリーアドレス導入に際して発生する課題は?
おすすめ資料 -

債権管理・入金消込効率化『Victory-ONE/G4』導入事例 ~入金消込の効率が飛躍的にアップ! ティーペック株式会社~
おすすめ資料 -

法人税対策・実物資産投資の新たな選択肢 最新情報掲載 『日本型オペレーティングリースガイドブック』
おすすめ資料 -
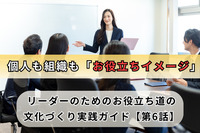
個人も組織も「お役立ちイメージ」/リーダーのためのお役立ち道の文化づくり実践ガイド【第6話】
ニュース -

「給与レンジ」を適切に設計。採用力や定着率を高める効果も
ニュース -
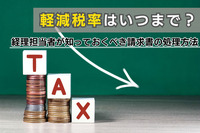
軽減税率はいつまで?経理担当者が知っておくべき請求書の処理方法
ニュース -

旬刊『経理情報』2026年2月10日号(通巻No.1767)情報ダイジェスト①/会計
ニュース -

従業員の副業における注意点|企業が知っておきたいリスクと対応策
ニュース -

契約書のリーガルチェックの重要性と6つのチェックポイント
おすすめ資料 -

サーベイツールを徹底比較!
おすすめ資料 -

英文契約書のリーガルチェックについて
おすすめ資料 -

【新卒採用トレンド】優秀な人事は押さえている!新卒採用3大トレンド
おすすめ資料 -

-ホンネを引き出し離職要因を解明- 退職者インタビューサービス資料
おすすめ資料 -

ファイル共有規程ひな形|禁止事項と運用術
ニュース -
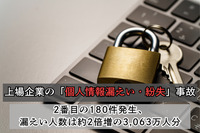
上場企業の「個人情報漏えい・紛失」事故 2番目の180件発生、漏えい人数は約2倍増の3,063万人分
ニュース -

弁護士解説:景表法違反で課徴金はいくら?対象行為・計算方法・回避策とは?
ニュース -

2026年4月「育休取得率・賃金格差」開示義務化直前!IPO審査で問われる数値の裏付け
ニュース -
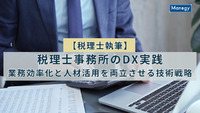
【税理士執筆】税理士事務所のDX実践──業務効率化と人材活用を両立させる技術戦略
ニュース