公開日 /-create_datetime-/
人事労務の業務効率化するホワイトペーパーを無料プレゼント
チェックしておきたい法令関連の情報やノウハウやヒントなど業務に役立つ情報をわかりやすくまとめた資料をご紹介します。全て無料でダウンロード可能ですので、是非ご活用ください。
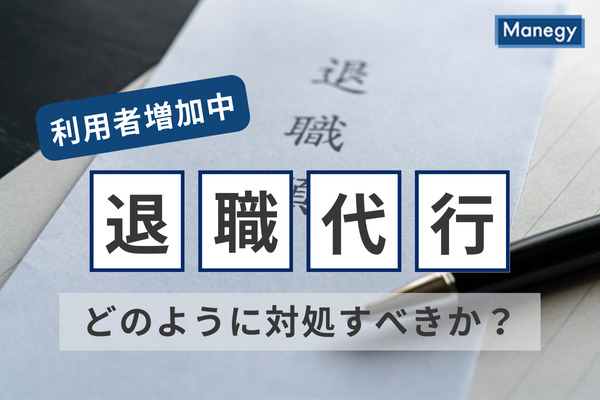
本人に代わって、会社に退職の意思を伝える「退職代行サービス」の利用者が増えています。今までは考えられなかったような新しい業種ですが、複数の企業がサービスを展開しています。
今後は企業の担当者も、代行サービスから退職願を受け取るケースがあるかもしれません。その時に混乱を来さないためにも、退職代行サービスへの対処法について考えてみましょう。
【関連記事】
退職代行サービスの知名度は92%!利用したことがある割合は?【退職代行に関する実態調査】
まず前提として、会社と社員を仲介して交渉を進められるのは、弁護士のような専門家に限られます。社員本人以外が会社に対してできることは、職場に退職届を手渡すことだけです。しかし状況は変わりつつあるようです。
退職代行サービス企業によっては、労働環境改善組合や退職代行ユニオンと提携しているケースがあります。この場合は会社に対して団体交渉権をもっているため、労使間の問題についても交渉が可能です。
また、弁護士事務所と提携しているケースもあります。実際の弁護士業務は代行できませんが、退職手続きに関する法的知識は、十分に備えていると考えた方がよいでしょう。
【関連記事】
急増する退職代行サービスの実態とは?「モームリ」運営企業が語る現状
退職代行サービスは歴史の浅い業種のため、法律面での対応があまり進んでいません。企業が対策を立てるためには、法務部門が法的な課題について検証するべきでしょう。
まず、代行サービス業者が退職届を持ってきたと仮定しましょう。これだけなら法的な問題はありません。ところが退職に関する条件交渉をした場合、その時点で違法の可能性が高くなります。法律事務所と提携していても、業者が直接交渉することは越権行為になるでしょう。
ただし、会社から社員に伝達事項がある場合、業者がそれを取り次ぐことは可能です。しかしこの際にも、業者が直接交渉をすると違法になる可能性があります。
つまり企業側としては、業者が直接交渉に臨むようなら対応する必要はないということです。ただし代行サービス側が、労働組合の組合員を派遣してきた場合は別です。この場合は団体交渉権の行使が認められます。
【関連記事】
退職代行サービスの現状と課題 専門家が語るリアルな現場
社員本人から直接でも、退職代行サービスを通じてでも、退職届が出されてから2週間の期間を設けて、会社側は退職を認めなければなりません。代行サービスから連絡があった時点で、退職届の受理は避けられないことになるでしょう。
会社は速やかに、社員本人の意思を確認する必要があります。どうしても本人と連絡がとれない場合は、退職代行サービスに委任状の有無を確認して、本人の意思を見極めるという方法もあります。
実際に退職代行サービスに対応する際には、弁護士もしくは労働環境改善組合・退職代行ユニオンが相手の場合、退職の条件交渉に応じたのち退職も認めなければなりません。拒否すると会社側が法的責任を問われる可能性があります。業者のみが相手の場合でも、本人の意思が確認できれば迅速に退職手続きを進めることになるでしょう。
【関連記事】
退職代行における弁護士の役割とは?弁護士が語る現状と課題
SNSなどの広がりによって、他人とのつながりが希薄な社会になったためか、会社を辞めるという意思表示も業者に任せる時代がやって来ました。管理職や人事担当者にとってはやるせない状況でしょう。
退職代行サービスの利用にかかわらず、まずは社員を退職に追い込むことがないように、普段から社員との関係を深めておくことが重要です。社員が辞めたくない職場づくりが、ベストな離職対策になるでしょう。
#退職代行
※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。

債権管理・入金消込効率化『Victory-ONE/G4』導入事例 ~30時間かかっていた入金消込がほんの数十秒に! 伊藤忠エネクス株式会社~

フリーアドレスの成功事例 ご紹介

【1on1ミーティング】効果的な実践方法と運用時のポイント

フランチャイズ契約を締結する前にチェックすべきポイントとは(加盟店の立場から)

郵便物の電子化による部署別 業務効率化事例
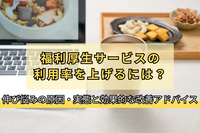
福利厚生サービスの利用率を上げるには?伸び悩みの原因・実態と効果的な改善アドバイス

【無料DL可】収入印紙管理表テンプレート|管理方法・使い方をわかりやすく解説
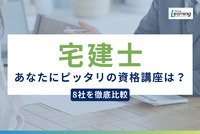
宅建士講座おすすめスクール徹底比較|価格・教材・サポート体制で選ぶ、あなたにぴったりのスクールは?
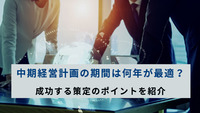
中期経営計画の期間は何年が最適?成功する策定のポイントを紹介

AIエージェントで加速する経営 取り残されないための戦略法務 実装ガイド

法人税対策・実物資産投資の新たな選択肢 最新情報掲載 『日本型オペレーティングリースガイドブック』

新卒エンジニア採用に20年投資し続けてわかったこと~代表取締役が語る新卒採用の重要性~

管理部門職種別 面接質問集【MS-Japan】

他社との違いは?電子契約サービスの比較検討ガイドのご紹介

株式会社I-ne導入事例~月間の受注データ件数は20万件以上!『 Victory-ONE【決済管理】』の導入で 業務効率化と属人化の解消を実現~

配偶者死亡時に受けられる2つの社会保険 ― 遺族年金・埋葬料の手続きと注意点 ―

KPIを行動に落とし込む方法|社員が動ける数字の使い方
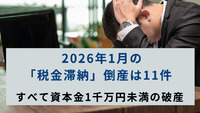
2026年1月の「税金滞納」倒産は11件 すべて資本金1千万円未満の破産
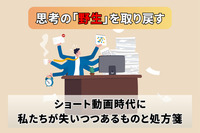
思考の「野生」を取り戻す―ショート動画時代に私たちが失いつつあるものと処方箋

DX導入後8割が「作業増えた」と回答 中小企業におけるDX推進、課題浮き彫り
公開日 /-create_datetime-/