公開日 /-create_datetime-/
法務のノウハウと課題可決のヒントが詰まっている資料を無料プレゼント!
電子署名や契約書作成・レビューなど効率化したい法務担当者がダウンロードした資料をまとめました。全て無料でダウンロードできるおすすめの資料を使って生産性を上げませんか?

2024年4月に国会で物流総合効率化法と貨物自動車運送事業法の改正法が成立しました。法律名の通り流通・運輸業者に関係するルールで、多くの日本企業にとって「物流」は切っても切り離せない領域であるため、基本知識として法改正の内容は理解しておきたいところです。
公布された2024年5月15日から1年以内に施行されるため、法律内容に直接関係する事業者は、それまでに対策を講じる必要もあります。 そこで今回は、物流総合効率化法と貨物自動車運送事業法の改正内容について詳しく解説します。
物流総合効率化法(流通業務の総合化および効率化の促進に関する法律)とは、2つ以上の事業者・法人の連携により、流通業務の一体化・輸送の合理化を促進させるための法律です。具体的には、法律内容に沿った流通業務の効率化・省力化の計画を立てた事業者に対して、国が支援することを定めた内容です。
この法律の下では、たとえば2つ以上の物流事業者が業務の効率化・省力化のため、「輸送網の集約」「輸配送の共同化」「モーダルシフト(貨物輸送をトラックから環境負荷の小さい鉄道、船舶に転換すること)」などに取り組む事業計画を立てた場合、国土交通大臣の認定を経て、国から支援措置を受けられます。同法が規定する支援措置は以下の4点です。
・事業の立ち上げ・実施の促進・・・計画策定経費や運行経費への補助、事業を始めるに当たっての、倉庫業や貨物自動車運送事業等の許可の「みなし」(許可を得ているとみなすこと)
・必要な施設や設備等への支援・・・輸送連携型倉庫に対する税制特例、施設の立地規制への配慮。
・金融支援・・・信用保険制度の限度額拡充、長期低利子貸付制度、長期無利子貸付制度(主に中小企業を対象)。
・独立行政法人鉄道・運輸機構(JRTT)による支援・・・事業実施に必要な資金の貸し付け。
以上のように、改正前の物流総合効率化法は、物流の効率化・省力化に資する事業の計画・実施を支援するための法律といえます。
貨物自動車運送事業法とは、トラックをはじめとする貨物自動車を使用して運送業を行う際の、許可制や行為規制などを定めた法律です。貨物自動車運送事業には「一般貨物自動車運送事業」「特定貨物自動車運送事業」「貨物軽自動車運送事業」の3種類があり、それぞれ同法によって許認可方法が規定されています。
・一般貨物自動車運送事業・・・他人の要求に基づき、運賃を受け取って自動車により貨物を運送する事業のことで、事業を行うには国土交通大臣の許可が必要。荷主は不特定で、依頼に応じて輸送を行う形態です。
・特定貨物自動車運送事業・・・特定の人の要求に基づき、運賃を受け取って自動車により貨物を輸送する事業のことで、事業を行うには国土交通大臣の許可が必要。「特定の人」とは、荷主が特定されていることを指します。
・貨物軽自動車運送事業・・・他人の要求に基づき、運賃を受け取って軽自動車もしくは125cc超の自動二輪車で貨物を輸送する事業のことで、事業を行うには国土交通大臣への届出が必要。上記の2事業は「許可」ですが、こちらは「届出」です。
今回の物流総合効率化法、改正貨物自動車運送事業法の改正内容は以下の通りです。なお、これまでの物流総合効率化法については、今回の法改正によって「流通業務総合効率化法(物資の流通の効率化に関する法律)」へと名称が変更されるので、この点に注意が必要です(施行は2025年5月なので、それまでは物流総合効率化法)。
●物流事業者に対して、物流の効率化のために取り組むべき措置について努力義務を設定(同法34条、52条)・・・雇用する運転者への負担を軽減するため、運転者1人につき運送1回ごとの貨物重量を増加させるべく、輸送網の集約や輸配送共同化などの措置を講じることが努力義務化。
●荷主に対しても、同様の目的により物流事業者に協力することが努力義務化(同法42条)。
●連鎖化事業者(フランチャイザー)に対しても、同様の目的により貨物の受け渡しを実施する日時等に関して、一定の措置を講じることが努力義務化(同法61条)。ここでいう連鎖化事業者とは、コンビニのようなフランチャイズチェーン店の本部を指します。
現行法では、国が促進したい「効率化・省力化」を実現した事業を支援する内容がメインですが、改正法は努力義務を含む規定が新たに盛り込まれています。その点も踏まえて法律の名称も変わったと考えられます。
●元請け事業者に対して、実運送事業者の名称等が記載された「実運送体制管理簿」の作成を義務化。
●荷主・運送事業者に対して、運送契約の締結をする際に、提供するサービスの内容とその対価(業務量、燃料サーチャージ等を含む)について記載した書面の交付等を義務化。
●運送事業者に対して、他の事業者の運送を利用する(下請けに出す)行為への適正化を努力義務化。また「一定規模以上」の事業主に対して、この適性化に関する管理規定の作成、責任者の選任を義務化。
●軽トラック事業者に対しては、法律知識を得るための管理者を選任して講習を受講することが義務化、国土交通大臣への事故報告が義務化。
●国土交通省の公表対象として、軽トラック事業者の事故報告、安全確保命令に関する情報を追加
改正貨物自動車運送事業法においても、義務化・努力義務化の項目が多数追加されました。また今回の改正法では、流通業務の効率化・省力化に寄与する必要がある者として、「一定規模以上」の物流事業者、荷主、倉庫業者、連鎖化事業者が「特定事業者」と位置付けられました。
細かい指定基準については、政令によって定めていくとされています。なお、義務化の規定に違反した場合は、最大100万円の罰金等が課されます。
今回の法改正実施の念頭にあるのは、いわゆる「物流の2024年問題」です。物流の2024年問題とは、法制度の変更によりトラック運転者の時間外労働が規制されることで、労働力不足となり、日本全体の物流が機能不全を起こす恐れがある問題・懸念のことです。
国としては、ドライバー1人当たりの労働時間が大幅に減っている中、物流に関わる事業者に対してこれまで以上に効率化・省力化を実現してもらいたいのです。そのため「努力義務」「義務化」の文言が並ぶ法改正になったといえます。また軽トラック運送事業者への規制強化は、昨今の軽トラックによる事故増加が背景にあるでしょう。
#物流総合効率化法 #物流 #効率化法 #貨物自動車運送事業法 #2024年問題
■参考サイト
物流2024年問題、トラック運転手の賃金を24年度から10%前後引き上げる政府方針
物流の2024年問題とは? 制定の背景と影響を徹底解説
建設業2024年問題の実態調査、時間外労働上限規制完全実施は4割以下という実情
2024年問題対策!建設業・運輸業界で使える補助金【東京都】
※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。

WEBサイト製作の業務委託契約書の作成方法と注意点

新卒エンジニア採用施策アイデア大全

総務・経理・営業の生産性に影響する法人車両の駐車場管理における落とし穴

工事請負契約書とは?作成時の注意点などを解説!

サーベイツールを徹底比較!
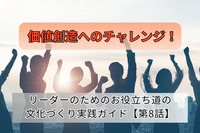
価値創造へのチャレンジ!/リーダーのためのお役立ち道の文化づくり実践ガイド【第8話】

管理部門の今を知る一問一答!『働き方と学習に関するアンケート Vol.3』
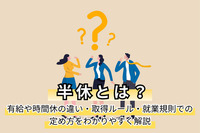
半休とは?有給や時間休の違い・取得ルール・就業規則での定め方をわかりやすく解説
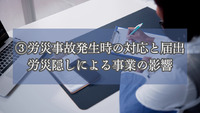
③労災事故発生時の対応と届出│労災隠しによる事業の影響
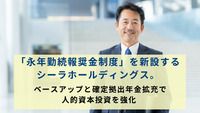
「永年勤続報奨金制度」を新設するシーラホールディングス。ベースアップと確定拠出年金拡充で人的資本投資を強化

郵便物の電子化による部署別 業務効率化事例

消費者契約法で無効にならないキャンセルポリシーの作成方法

業務委託契約の基本がわかるハンドブック

【スキル管理のメリットと手法】効果的・効率的な人材育成を実践!

採用力・定着率を強化し、法定福利費も削減。 "福利厚生社宅"の戦略的導入法を解説

『不調になってから』では遅い Smart相談室が描く、個人と組織の成長が一致する職場のつくり方

2026年版「働きがいのある会社」ランキング発表 全部門で日系企業が首位を獲得

衆院選の争点 「内需拡大の推進」41.8%政党支持率は、大企業と中小企業で違いも

労基法大改正と「事業」概念の再考察 ~事業場単位適用の実務~

②労災事故発生時の対応と届出│労働者死傷病報告提出のタイミング~労働者死傷病報告の方法と内容
公開日 /-create_datetime-/