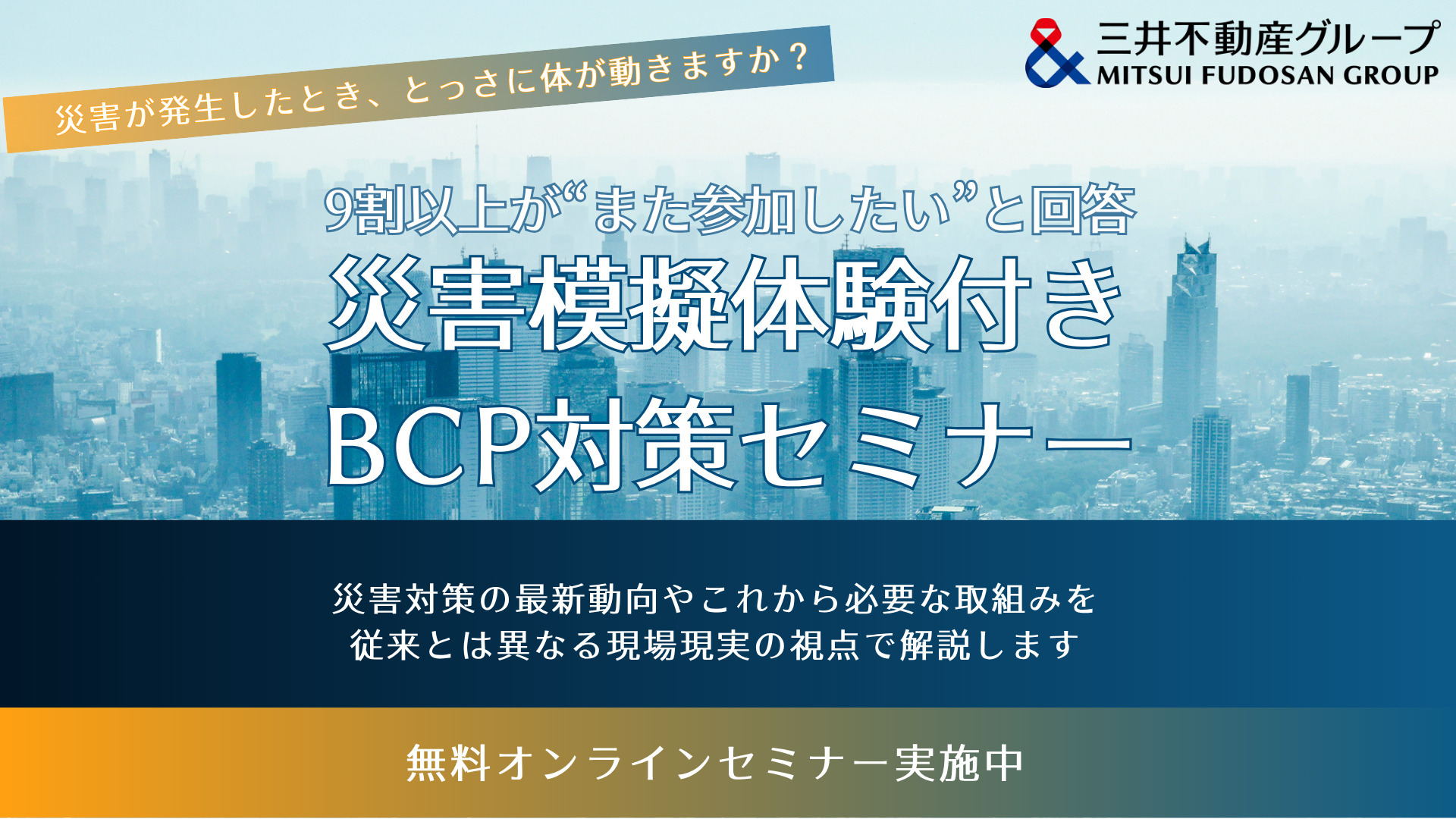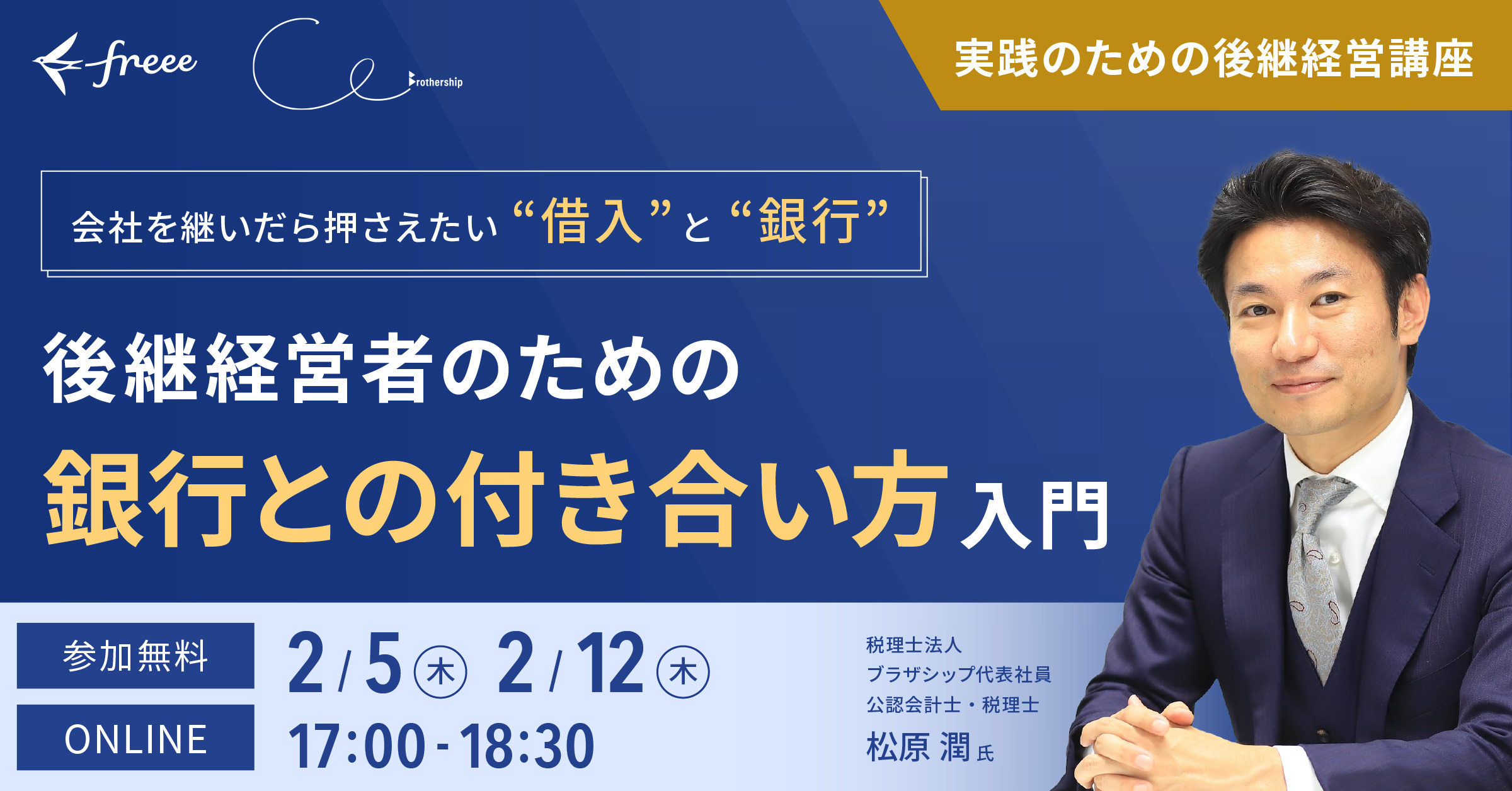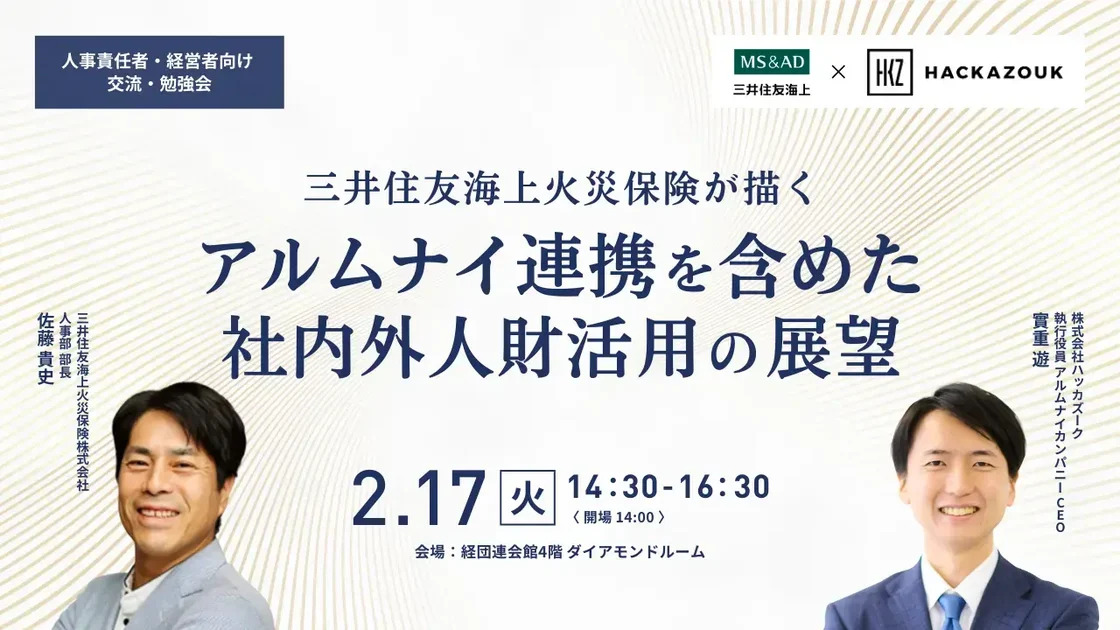公開日 /-create_datetime-/
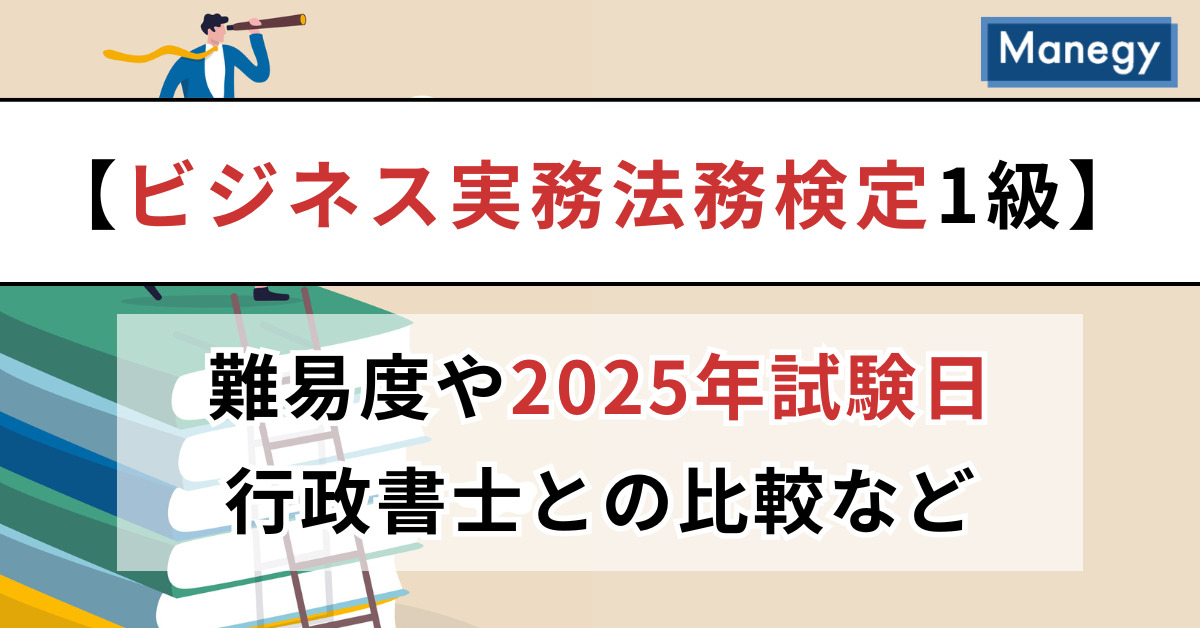
近年、ビジネスに役立つ法律知識を証明する手段の一つとして「ビジネス実務法務検定」が注目されています。
その中でも1級は企業法務に関する高度な専門知識が求められるため、合格を目指すには入念な準備が欠かせません。
受験を検討するうえで難易度を把握しておくことも大切です。さらに、学習範囲が一部重なる行政書士の取得を視野に入れるのも有効です。
本記事では、ビジネス実務法務検定1級の合格率・試験日程・合格メリットなど、受験前に知っておきたい情報を整理しました。
目次本記事の内容
ビジネス実務法務検定とは
ビジネス実務法務検定は東京商工会議所が主催する民間資格で、企業活動に必要な法律知識を体系的に学べます。
試験区分は3級・2級・1級の3つで、3級は法律の基礎、2級は実務への応用、1級は高度な専門知識と法的判断力が問われます。
いずれも受験資格制限はなく、2級以上の取得は転職市場で評価されやすいといわれます。
近年、コンプライアンス意識の向上や企業のリスク管理強化が進む中、法的知識を持つ人材への需要は高まり、社内研修として当検定を奨励する企業も増えています。
ビジネス実務法務検定1級の合格率・難易度
ビジネス実務法務検定1級は、法務の専門知識を測る試験の中でも高い難易度を誇ります。
過去の合格率を見ても、合格することが簡単ではないことがわかります。
1級の合格率推移
直近3年の合格率は次のとおりです。
| 年度 | 実受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
|---|---|---|---|
| 2024年 | 445人 | 74人 | 16.6% |
| 2023年 | 467人 | 49人 | 10.5% |
| 2022年 | 481人 | 43人 | 8.9% |
データを見ると、2022年度から合格率は右肩上がりで推移しています。
これは、2022年から受験資格が緩和され、2級の合格者でなくても受験できるようになったことが一つの要因として考えられます。
1級と2級・3級の難易度の違い
ビジネス実務法務検定は階級レベルによって出題形式や試験時間が異なります。
2級・3級は90分の多肢選択式ですが、1級は論述式で90分×2部構成(計3時間)で行われます。論理構成力と文章力が要求されるうえ、試験時間も長く集中力維持が必須です。
また、合格率の比較を見ても、1級の難しさが際立っています。2024年度の2級合格率は38.1%、3級は43.5%でした。
1級の16.6%と比べると、2級や3級は合格しやすい傾向にあると言えるでしょう。
1級で求められるスキル
1級では、法律の知識を単に覚えるだけではなく、実際の業務にどう活用するかを考える力が試されます。
企業法務に関する幅広い知識を身につけた上で、具体的な事例に対して適切な判断ができるようになることが重要です。
試験では六法全書の持ち込みは可能ですが、条文を参照できるからといって試験が簡単になるわけではありません。
法律の条文を読み解き、実務の観点からどのように適用すべきかを考えながら解答する力が必要とされます。
合格を目指すために
1級に合格するためには、計画的に学習を進め、実践的な知識を身につけることが求められます。
論述式の試験に慣れるために、過去問や模擬問題を解きながら、論理的に解答を組み立てる練習をするとよいでしょう。
合格率が低い試験ではありますが、継続的に学習を積み重ねることで、合格を目指すことは十分可能です。
2025年ビジネス実務法務検定の試験日・合格発表はいつ?
2025年度1級の公式スケジュールは次のとおりです。
申込期間
2025年11月4日(火)〜11月11日(火)
受付期間は1週間と限られているため、申し込みのタイミングを逃さないよう注意が必要です。
試験日
2025年12月7日(日)
試験はCBT形式で実施され、全国のテストセンター設置PCを使用します。
共通問題90分+選択問題90分の2部構成です。
合格発表
1級は後日メール通知で発表されます(2級・3級の即時判定とは異なります)。
ビジネス実務法務検定1級と行政書士を比較
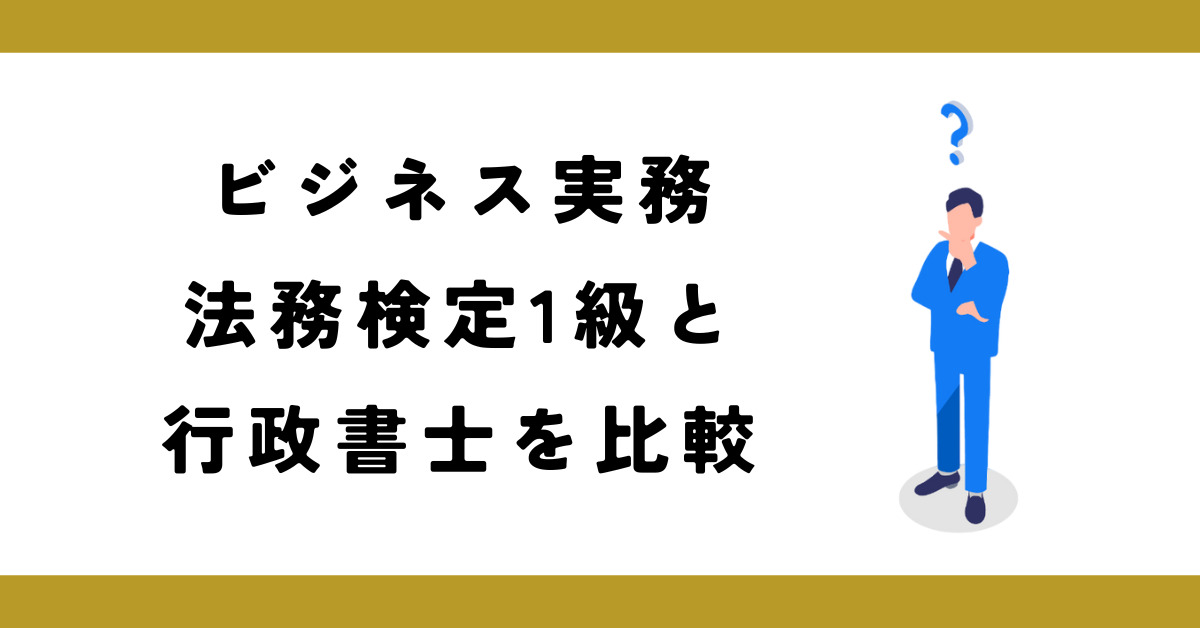
両試験は共に受験資格がなく法律知識を測る点で共通しますが、目的と難度が異なります。
2024年度結果の比較
| 実受験者数 | 合格者数 | 合格率 | |
|---|---|---|---|
| ビジネス実務法務検定 1級 |
445人 | 74人 | 16.6% |
| 行政書士 | 47,785人 | 6,165人 | 12.9% |
ビジネス実務法務検定1級の合格率は16.6%で、行政書士の12.9%と比較して高いものの、どちらの試験も難易度の高い試験です。
受験者数は行政書士に比べて非常に少なく、専門性の高さがうかがえます。
受験者層と試験の特性
行政書士試験は法律系の国家資格の一つであり、幅広い法律知識が求められます。
試験範囲は憲法・行政法・民法・商法など広範囲にわたり、容易に合格できる資格ではありません。
一方、ビジネス実務法務検定1級は、企業法務に関する知識を問う民間資格であり、実務で役立つ知識の習得が特徴です。
合格率の低さからもわかるように、高度な法務知識が必要であり、企業法務に携わる人が受験する傾向があります。
難易度の観点
行政書士試験は受験者数が多いため、合格者数も一定数確保されています。
一方、ビジネス実務法務検定1級は受験者が少なく、合格率も低いため、より専門的な知識と実践力が求められる試験と言えます。
国家資格と民間資格の違いはあるものの、両者の比較から、ビジネス実務法務検定1級が決して難易度の低い資格でないことは明らかです。
行政書士は独立開業を視野に入れやすい一方で、ビジネス実務法務検定1級は企業の法務部門でキャリアアップを目指すのに適しています。
ビジネス実務法務検定の「準1級認定制度」とは?
ビジネス実務法務検定1級には、「準1級認定制度」が設けられています。
これは、1級を受験したものの合格基準には達しなかった受験者のうち、一定の条件を満たす人に対して「準1級」として認定する仕組みです。
具体的には、1級の合格点は200点満点中140点ですが、以下のいずれかの条件に該当する受験者が「準1級」と認定されます。
・139点〜110点を獲得した場合
・140点以上を獲得したものの、共通問題2問・選択問題2問のいずれかで50%未満だった場合
この制度により、1級に不合格だった場合でも、1級に準ずる実力があることが証明されます。
転職市場やビジネスの場では、2級以上が評価されやすい傾向にありますが、準1級であればより専門的な知識を備えていることをアピールしやすくなります。
これから法務への転職を目指す人にとっては、準1級の認定も大きな意味を持つはずです。
1級の合格を目指す場合でも、まずは準1級のステップを踏むことで、次の試験へのモチベーションにつなげられるでしょう。
ビジネス実務法務検定1級を取得するメリットとは?
ビジネス実務法務検定には、司法書士や行政書士のような独占業務がないため、合格しても「意味がない」と言われることがあります。
しかし、1級に合格することで、さまざまなメリットが得られることも事実です。
法律知識を活かしてトラブルを回避しやすい
ビジネス実務法務検定1級では、法務の実務に必要な知識を深く学びます。
契約書の精査や取引先との交渉において、リスクを事前に察知しやすくなり、トラブルを未然に防ぐ判断力が養われます。
企業内で法務を担う立場にある場合、この知識を活かせる場面は少なくないでしょう。
他の法律系資格の学習にも役立つ
ビジネス実務法務検定1級の試験範囲は、司法書士や行政書士といった国家資格の学習内容と重なる部分があります。
そのため、1級合格をきっかけに、さらに高度な法律資格へ挑戦する人も珍しくありません。
法務の専門性を高めたい場合、その土台として活用しやすいでしょう。
まとめ
ビジネス実務法務検定1級は、法律の専門知識が問われる難易度の高い資格です。合格すれば法務の実務に役立ち、スキルアップにもつながるでしょう。
転職活動の際、履歴書の資格欄に記載するだけでは十分なアピールとは言えません。
実際の業務でどのように知識を活かせるのか、自身の強みとしてどう伝えるかが重要です。
アピール方法に不安がある場合は、法務特化型転職エージェントに相談するとよいでしょう。
法務求人の紹介はもちろん、キャリア相談を通じて適切な自己PRの方法をアドバイスしてもらえます。
さらに、応募書類の添削や面接対策のサポートも受けられるため、法務への転職を目指す方にとって心強い味方になります。
「MS Agent」のような法務の転職支援に強いエージェントを活用し、キャリアの可能性を広げてみてはいかがでしょうか。
Manegyの法務オススメ記事
MS Agentの関連オススメ記事
※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。
MS Agentに掲載中の求人
おすすめコンテンツ
新着おすすめセミナー
人気記事ランキング
キャリア記事ランキング
新着動画
関連情報
-

契約書のリーガルチェックの重要性と6つのチェックポイント
おすすめ資料 -
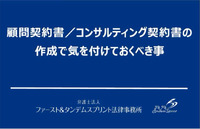
顧問契約書/コンサルティング契約書の作成で気を付けておくべき事
おすすめ資料 -

フランチャイズ契約を締結する前にチェックすべきポイントとは(加盟店の立場から)
おすすめ資料 -

紙書類と郵送物の電子化によるコスト削減効果
おすすめ資料 -

アフターコロナの採用戦略とコスト最適化
おすすめ資料 -

【あなたは分かる?】「基準」と「規準」の意味の違い|正しい使い方や例文を完全解説!
ニュース -

ライセンス契約とは?主な種類・OEM契約との違い・契約書の記載項目までわかりやすく解説
ニュース -

2025年の「負債1,000万円未満」倒産 527件 3年ぶり減少も2年連続の500件台で高止まり
ニュース -

OEM契約とは?メリット・デメリットからOEM契約書の重要条項まで整理
ニュース -
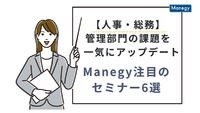
【人事・総務】管理部門の課題を一気にアップデート。Manegy注目のセミナー6選
ニュース -

健康経営ソリューションとして 社宅・社員寮が果たす役割
おすすめ資料 -

オフィスステーション年末調整
おすすめ資料 -

新卒エンジニア採用施策アイデア大全
おすすめ資料 -

業務委託契約書の書き方のポイントは?知っておくべき基礎知識
おすすめ資料 -

経理業務におけるスキャン代行活用事例
おすすめ資料 -
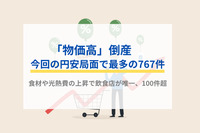
「物価高」倒産 今回の円安局面で最多の767件 食材や光熱費の上昇で飲食店が唯一、100件超
ニュース -
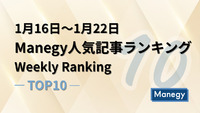
1月16日~1月22日のManegy人気記事ランキング|Weekly Ranking TOP10
ニュース -
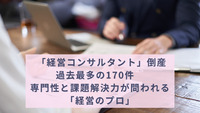
「経営コンサルタント」倒産 過去最多の170件 専門性と課題解決力が問われる「経営のプロ」
ニュース -
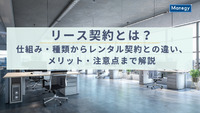
リース契約とは?仕組み・種類からレンタル契約との違い、メリット・注意点まで解説
ニュース -
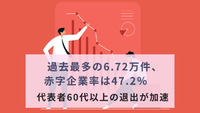
過去最多の6.72万件、赤字企業率は47.2% 代表者60代以上の退出が加速
ニュース