公開日 /-create_datetime-/
経理財務限定!業務に役立つ資料を無料プレゼント
業務過多や属人化などの課題を解決する資料から経費精算の効率化など業務に役立つ資料をプレゼント。また法令関係など正しく理解しておきたい方に向けた資料もご用意しております。すべて無料でダウンロードできます。
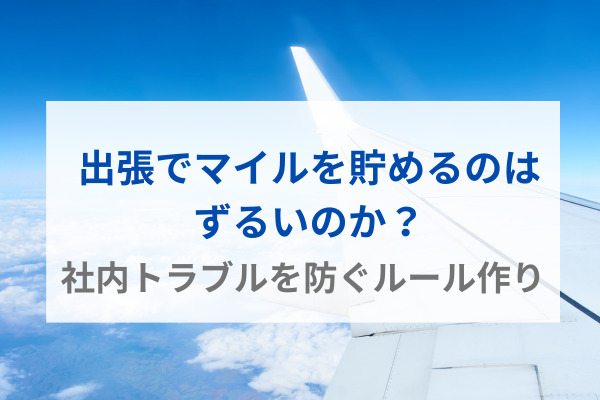
出張で頻繁に飛行機を利用する社員が個人マイルを貯めていることに、同僚から「ずるい」と感じられるケースが少なくありません。
出張費は会社が負担しているのに、得られるマイルが社員個人に帰属する点が、公平性を欠くように見えるためです。
こうした不満を防ぐためには、出張マイルの扱いを明確にし、社内ルールとして整備しておくことが重要です。
本記事では、管理部門・士業の立場から、出張マイルをめぐるトラブル防止策と実務対応のポイントを解説します。
前述したように、出張で飛行機を利用する社員が個人マイルを貯めることを「ずるい」と感じるケースは少なくありません。
SNSでも「会社の出張で貯めるマイルはずるい」「経費で行っているのに個人の利益になるのはおかしい」といった意見がたびたび見られます。
一方で、長時間の移動や出張の負担を考慮すれば、「マイルくらいは社員のモチベーション維持に役立つ」という声もあります。
つまり「ずるい」とは感情的な問題であると同時に、ルール設計や情報の非共有によって生じる不透明さの問題でもあります。
管理部門としては、モラルの問題にとどめず、制度的に整理しておくべきテーマといえるでしょう。
航空会社が提供するマイレージサービスは、飛行距離や利用金額に応じてマイルを付与する仕組みです。
出張時に利用した航空券の名義が社員個人であれば、その社員のマイレージ口座に自動的にマイルが積算されます。
また、会社のコーポレートカードや個人のクレジットカードで航空券を購入した場合には、カード会社のポイントも別途付与されることがあります。
つまり、支払元と搭乗者の両方が異なる場合、実質的に「会社負担で社員がポイントを受け取る」構造が生じやすいのです。
このため、企業がルールを定めずに運用すると、後から「不公平」「私的利用ではないか」といった問題に発展する可能性があります。
出張で発生するマイルは、会社が管理するか、社員個人に任せるかで扱いが大きく変わります。
どちらの方法にもメリットとデメリットがあり、企業の規模や出張頻度に応じて最適な運用を選ぶことが重要です。
会社が航空券を手配すれば、従業員個人にマイルが付与されるのを防げます。
一方、従業員が個人のクレジットカードで手配した場合は、付与されたマイルの報告を義務付け、経費精算時に取得マイルも申告するよう周知します。
私的利用禁止の方針に違反した場合は、適切な対応が必要です。
一方で、搭乗者名義が社員個人の場合、自動的にその人のマイレージプログラムに加算されます。
多くの企業では出張マイルの個人利用を黙認しており、「社員の福利厚生の一部」として扱うケースもあります。
しかし、全社員の理解が得られないと、「出張に行く人だけ得をしてずるい」という不満の火種になります。
実際、経費精算の過程で「マイル分を換算して差し引くべきでは」と指摘されたり、内部通報につながるケースもあります。
このような事例を防ぐためには、会社として方針を明文化し、あらかじめ社内で共有しておくことが重要です。
あわせて読みたい
A. 会社のルールによります。
旅費規程や就業規則に「会社帰属」と記載があれば個人利用は避けるべきです。
明記がない場合は、総務部門に確認しましょう。
A. 航空券の購入方法によって大きく異なります。
搭乗で貯まるフライトマイル: 飛行距離や運賃クラスによって異なり、一律の計算はできません。
例えば、東京〜ニューヨーク往復のエコノミークラスで約10,000〜13,000マイル程度が目安です。
クレジットカード決済で貯まるマイル: 一般的なマイル還元率は0.5〜1.0%です。100万円分の航空券をクレジットカードで購入した場合、約5,000〜10,000マイル相当が貯まる計算になります。
ただし、航空会社提携カードや特約店利用などで還元率が上がる場合もあります。
詳しくは各航空会社の公式サイトをご確認ください。
A. 公務員のマイル取得については、省庁や自治体によって対応が異なります。
会計検査院や法務省、防衛省などは公務出張でのマイル取得を禁止または制限していますが、外務省をはじめ多くの省庁では「個人の判断」として容認しています。
ただし、取得を認める場合でも「次回以降の公務に利用すること」を推奨するガイドラインを設けている組織が多く、私的利用については慎重な対応が求められます。
詳しくは、所属する組織の規定を必ず確認してください。
出張マイルをめぐる「ずるい」という声は、社員の感情だけでなく、制度の不明確さが引き起こす組織課題です。
管理部門・士業の立場としては、公平性と説明責任を両立させる仕組みを整えることが求められます。
マイルの帰属先をどうするか、判断基準をどこに置くかを明文化し、定期的に周知することで、社員間の信頼を維持できます。
感情的な不満を制度で防ぐ――それが健全なガバナンスを実現する第一歩です。
あわせて読みたい
※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。

「チェックリスト付き」電子契約サービスの失敗しない選び方

経理業務におけるスキャン代行活用事例

シニア雇用時代の健康管理の備えとは? 健康管理見直しどきナビ

法人税対策・実物資産投資の新たな選択肢 最新情報掲載 『日本型オペレーティングリースガイドブック』

株式譲渡契約書とは?記載事項や作成時の注意点について解説!

新型コロナ破たん、1月は一転して150件割れ

①労災事故発生時の対応と届出│「労災隠し」とは

不動産業界の定説を覆す「営業社員の土日祝休み」導入 三井不動産レジデンシャルのデジタル改革

役職定年・定年延長時代に問われる「シニア人材マネジメント」 ―45〜60歳を“戦力”にできる組織、できない組織の分かれ道

産業医の探し方|初めての選任で失敗しない4つのポイント

業務委託契約(Service Agreement)の英文契約書を作成する際の注意点を弁護士が解説

オフィスステーション年末調整

アフターコロナの採用戦略とコスト最適化

土地建物売買契約書の見直し方法と5つのチェックポイント

WEBサイト製作の業務委託契約書の作成方法と注意点

人事異動はどう考える?目的別の判断軸と現場に納得される進め方

2026年1月の「人手不足」倒産 36件 春闘前に「賃上げ疲れ」、「人件費高騰」が3.1倍増

【日清食品に学ぶ】健康経営は「福利厚生」から「投資」へ。手軽に導入できる「完全メシスタンド」とは【セッション紹介】

7割の企業がファンづくりの必要性を実感するも、約半数が未着手。

今、何に貢献しますか?/リーダーのためのお役立ち道の文化づくり実践ガイド【第7話】
公開日 /-create_datetime-/