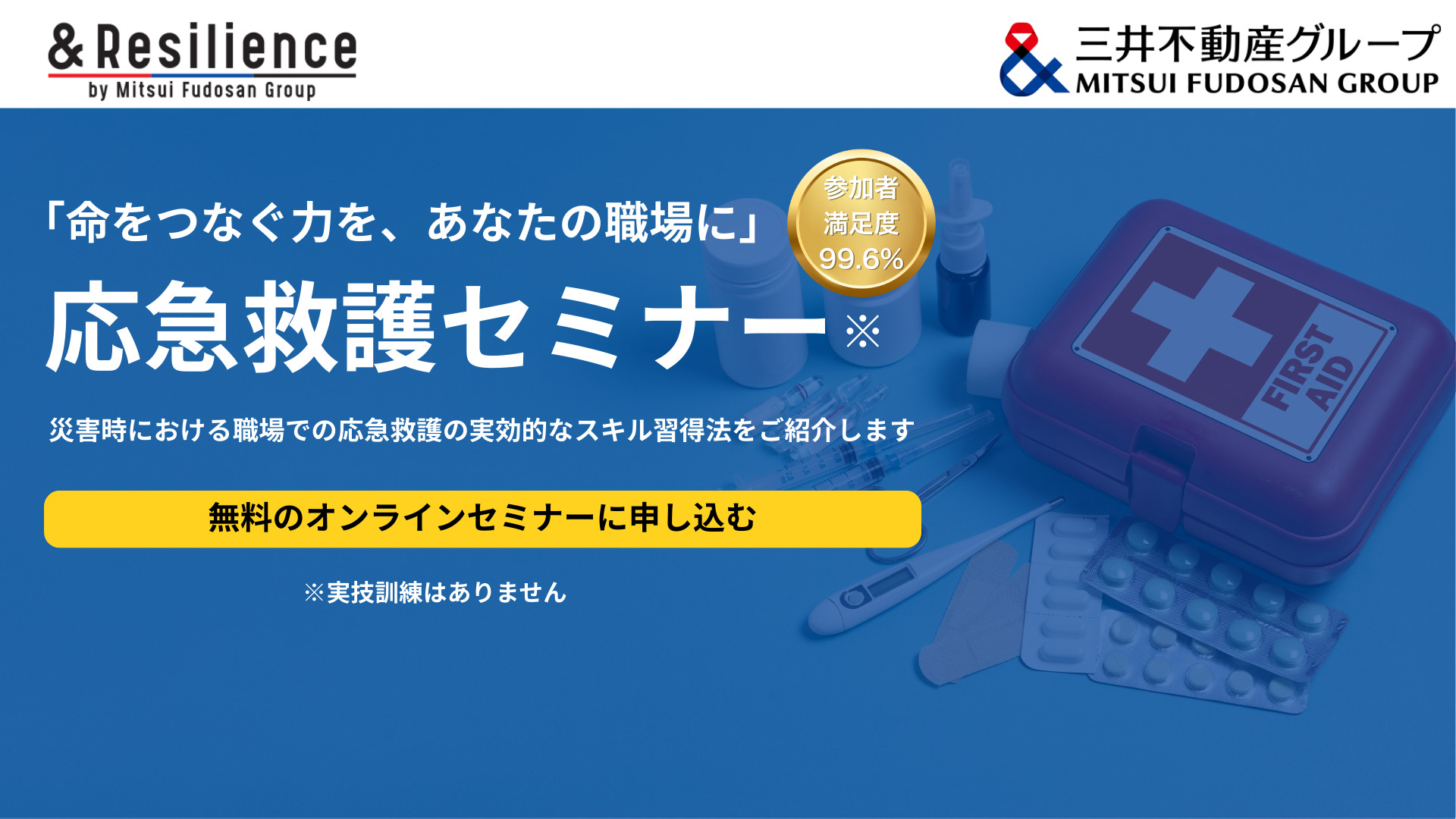公開日 /-create_datetime-/
パワハラと指導の違い

権限を持つ上の立場にいる人間が、弱い立場にある下の人間に対して力を背景に人権侵害を行うパワハラは、決して許されるべき行為ではありません。ただ、職場においては上司や先輩は部下に対して「指導」を行う必要があります。その際、時には叱責を伴うこともあるでしょう。ミスをした部下を注意して、本人が嫌な思いをしたら、それはパワハラとなるのでしょうか?
今回は、パワハラと指導の違いは何か、職場ではどのような行為がパワハラとなるのか、について詳しく解説します。
パワハラとは・・・厚生労働省が定めている類型
厚生労働省の資料によると、パワハラとは以下のように定義づけられています。
同じ職場内で働く人に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為をいう(厚生労働省『これってパワハラ?』より)。
この定義におけるポイントは、「職場内の優位性を背景としている」、「業務の適正な範囲を超えている」、「身体的または精神的な苦痛を与えている、もしくは就業環境を害している」の3点すべてを満たすものと定めている点です。例えば上司による部下への指導は、職務上の地位に基づく「職場内の優位性」を背景に行われます。ただ、その教育が業務の適正な範囲である場合、つまり本来の業務上必要性のある行為、方法・手段が社会通念に照らして許容される行為であるならば、パワハラには該当しないわけです。
では、この定義における「業務の適正な範囲を超える行為」、「身体的または精神的苦痛」とは具体的にどのような行為でしょうか。厚生労働省は、職場のパワハラに該当する行為を以下の6つの類型にまとめています。
①身体的な攻撃(暴行や障害)
②精神的な攻撃(脅迫や名誉棄損、ひどい暴言など)
③人間関係からの切り離し(仲間外れにする、無視するなど)
④過大な要求(遂行不可能なことを強制する、仕事の邪魔をするなど)
⑤過少な要求(能力や経験に見合わない程度の低い仕事を命じる、仕事をさせないなど)
⑥プライバシーの侵害(プライベートな事柄に過度に立ち入るなど)
パワハラと判断することには難しい面もある
実際の職場では、何がパワハラなのか分かりにくい面があるのも事実です。東京都労働相談センターが行った調査では、「パワハラが起きた時に対応が困難と感じること」について企業側に尋ねたところ、最も多かった回答が「パワハラと業務上の指導との線引きが難しい」(64%)でした。企業としても、パワハラと指導はどこが異なるのか、よく分かっていないのが現状なのです。
パワハラと指導の違いとは?
パワハラと指導の最大の違いは、どのような目的を持って行われているか、という点にあります。先ほどご紹介した厚生労働省の定義でも、「業務上の適正な範囲を超えていること」がパワハラの要件として挙げられていました。つまり、業務目的に沿った注意や叱責である場合、例えば部下の成長を促すため、業務状況の改善を促すためである場合は、パワハラではなく指導に該当します。
しかし、部下を無能呼ばわりすること、退職させること、晒し者にすること、上司の個人的な望みを達成することを目的とした行為は、すべてパワハラです。名目上は「業務目的のため」といっても、これらの要素も目的に加味されているならばパワハラとみなされます。
さらに、上司の言動・行動によって部下・職場環境がどう変化したかという点も、パワハラと指導を分ける重大な要素です。上司の注意、叱責により部下が過度に委縮する、職場の雰囲気が悪化して退職者が増加する、などの影響が出れば、上司の行為はパワハラに該当します。一方、注意したことで部下がより責任感を持って大きな仕事ができるようになった、職場が活性化されて業務状況が改善した、という場合は、上司の言動・行動は適正な指導といえるでしょう。
パワハラであると考えられる具体的なケース
例えば、個人に対する叱責メールを部署内に一斉送信する行為は、パワハラと判断されるのが通例です。ミスをした部下に対して「あえて衆人環視の中で厳しく叱責する」という行為は当然パワハラとなりますが、実際には人前ではなくとも、職場全員に一斉メールを送ることはそれと同等の「精神的攻撃」とみなされ、指導の範疇を超えます。
また、上司が部下に対して、SNSをしないよう命令することはプライバシーの侵害と判断され、パワハラとみなされるのが一般的です。、部下がツイッターで会社の営業妨害をするようなツイートをしている場合、「不適切な文言を削除するように」と注意するのであれば、指導の範疇に入るでしょう。しかし、「ツイッターを一切するな」といった命令は、部下のプライバシーに侵入する言動に当てはまります。
まとめ
管理者の方は、部下に対して指導を行い、時として注意・叱責をする必要性も生じるでしょう。しかし先に挙げた職場におけるパワハラの定義、6類型の行為に当てはまる振る舞いや言動を行った場合、部下からパワハラとして糾弾される恐れがあります。管理者は部下への注意の仕方には十分に気をつける必要があり、企業側としても管理者に対して必要な研修を実施しておく必要があるでしょう。
また、部下の側としてもパワハラを感じたら、別の上司や同僚、企業内にある相談窓口に相談する、あるいは都道府県に設置されている総合労働相談コーナーなどの公的機関に相談するなどの対策を行いましょう。
※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。
おすすめコンテンツ
新着おすすめセミナー
人気記事ランキング
キャリア記事ランキング
新着動画
関連情報
-

シニア雇用時代の健康管理の備えとは? 健康管理見直しどきナビ
おすすめ資料 -

管理部門職種別 面接質問集【MS-Japan】
おすすめ資料 -

フランチャイズ契約を締結する前にチェックすべきポイントとは(加盟店の立場から)
おすすめ資料 -

経理・人事・法務のスキルと年収相関の完全ガイド【MS-Japan】
おすすめ資料 -

優秀な退職者を「もう一度仲間に」変える 人材不足時代の新採用戦略
おすすめ資料 -

AI時代のスキルと人材育成 ~AIが代替できない「深化」の正体とは?~
ニュース -
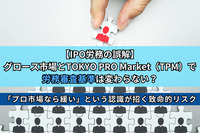
【IPO労務の誤解】グロース市場とTOKYO PRO Market(TPM)で労務審査基準は変わらない?「プロ市場なら緩い」という認識が招く致命的リスク
ニュース -
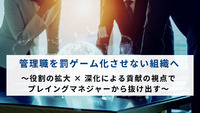
管理職を罰ゲーム化させない組織へ ~役割の拡大 × 深化による貢献の視点でプレイングマネジャーから抜け出す~
ニュース -

内定者研修の進め方ガイド|目的・内容・実施時期と注意点を整理
ニュース -
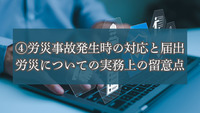
④労災事故発生時の対応と届出│労災についての実務上の留意点
ニュース -

契約不適合責任とは?売買契約書で 注意すべきポイントについて
おすすめ資料 -

上場企業・IPO準備企業必見!! 内部統制・監査の妨げになるアナログな入金消込とは
おすすめ資料 -

金融業界・製造業界 アルムナイネットワーク事例集
おすすめ資料 -

【スキル管理のメリットと手法】効果的・効率的な人材育成を実践!
おすすめ資料 -

英文契約書のリーガルチェックについて
おすすめ資料 -
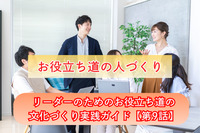
お役立ち道の人づくり/リーダーのためのお役立ち道の文化づくり実践ガイド【第9話】
ニュース -

25年のサイバー攻撃18%増、AIが悪用の主流に チェック・ポイントが最新リポート発表
ニュース -
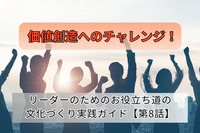
価値創造へのチャレンジ!/リーダーのためのお役立ち道の文化づくり実践ガイド【第8話】
ニュース -

管理部門の今を知る一問一答!『働き方と学習に関するアンケート Vol.3』
ニュース -
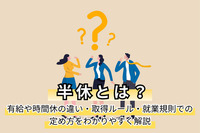
半休とは?有給や時間休の違い・取得ルール・就業規則での定め方をわかりやすく解説
ニュース