公開日 /-create_datetime-/
年末年始休業のお知らせ
2025年12月27日(土)~2026年1月4日(日)は年末年始休業のため、お問合せなどのご連絡は1月5日(月)以降になります。ご了承くださいませ。
定年後の社員に元気に活躍してもらう為に、人事担当者が知っておきたい再雇用制度
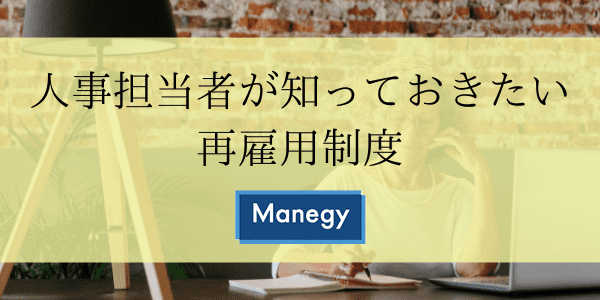
「再雇用制度」は、労働法の専門家以外には法律の解釈が複雑で分かりにくい面が多いといわれ、再雇用制度と勤務延長制度を混同しがちです。混同すると労使トラブルの原因にもなります。このため、人事担当者は法律の規制内容や厚生労働省のガイドラインを的確に反映した制度設計を行う必要があります。
再雇用制度とは
再雇用制度とは、2013年4月1日施行の「改正高年齢者雇用安定法(高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律)」に基づく「継続雇用制度」のうちの1つのこと。
同法は、65歳未満の定年制度を運用している企業に対し、次のいずれかの「高年齢者雇用確保措置」を義務付けています。
(1)定年年齢を65歳まで引き上げる
(2)希望者全員を対象とする65歳までの継続雇用制度を導入する
(3)定年制を廃止する
このうち(2)の継続雇用制度は、勤務延長制度と再雇用制度の2つに分かれています。
勤務延長制度は、定年年齢に達した社員が希望すれば、退職させずに雇用を継続する制度のことです。
一方、再雇用制度は定年年齢に達した社員に退職金を支払って定年退職させ、再雇用を希望した社員と雇用契約を新たに結び、雇用を継続する制度のことをいいます。
両制度の間には、基本的に次の違いがあります。
●勤務延長制度…定年退職手続きをしないので、賃金体系や労働条件は定年退職前と基本的に変わらない
●再雇用制度…いったん定年退職手続きをするので、賃金体系や労働条件は定年退職前と変わる
再雇用制度が注目されている理由
再雇用制度は元々、団塊の世代の大量退職による「2007年問題」への対応、年金支給開始年齢引き上げなどを背景とした高年齢者雇用安定の目玉施策として創設されました。しかし現在は働き方改革の見地から、経験豊富なシニア人材の有効活用を図る新たな人材マネジメントとして注目されています。
2013年4月の改正高年齢者雇用安定法施行直後の状況は、
1.企業の約80%が法的に義務付けられた高年齢者雇用確保措置として再雇用制度を導入
2.賃金は一律に定年退職前の60%程度、雇用形態は1年ごとに契約更新する嘱託社員
など一般的なパターンでした。
つまり、自社のシニア社員の活用については「法律に従って取り敢えず継続雇用制度を胴に有する。シニア社員の有効活用はそのうち考えよう」的な対応が、高年齢者雇用確保措置を迫られた企業側の実態だったといわれます。
この義務的対応により、企業には様々な問題が生じてきました。
最大の問題は、社員のモチベーションと労働生産性の低下でした。企業側に再雇用後のシニア社員の有効活用を図る展望や具体策が何もなかったため、再雇用後のシニア社員には一律的に労働生産性の低い定型的業務が割り当てられ、賃金も大幅減少したシニア社員は目標も遣り甲斐も持てず、飼い殺しのような気持ちで「遅れず、休まず、働かず」状態になったのです。
この影響で若手・中堅社員のモチベーションが低下、会社全体の活気を失った企業は珍しくないといわれます。また本来は外注化するような生産性の低い定型的業務をシニア社員に無理に割り当てたことにより、総人件費が却って膨らんだ企業も少なくないといわれます。
このような、法律に義務的に対応しただけの再雇用制度の問題の本質は、定年年齢で線引きをする硬直的な人材マネジメントにあります。
企業には豊富な業務経験と業務知識を持ったシニア社員だからこそ真価を発揮できる業務が少なくありません。例えば業務経験・技能の伝承、取引先および事業関連行政機関・公的研究機関・各種団体等外部ステークホルダとの折衝、中堅社員のOJT・バックアップなどです。
これらの業務の重要性を企業が認識していなかったことも、再雇用制導入の弊害をもたらしたといえます。
2019年4月から「働き方改革関連法」施行が順次開始され、働き方改革が本番を迎えました。柔軟で多様な働き方を実現する人事制度の抜本的改革の重要性が増しています。
この状況の中で、従来の年功序列制賃金体系を引きずった現在の単線型人事制度の欠陥が、再雇用制度の弊害という形で浮き彫りになりました。
再雇用制度は、シニア社員を含め年齢に関係なく社員の経験や能力に対応した役割と処遇を与える複線型人事制度への転換の必要性を実証したという意味において、注目されているといえるでしょう。
再雇用制度を導入する際の注意点
再雇用制度の導入に当たっては、法規面で注意しなければいけないいくつかの事項があります。
・再雇用の処遇
●退職前より著しく低い賃金は違法
現在導入されている再雇用制度の雇用契約は、60歳で定年退職した社員を65歳まで1年契約の有期雇用を更新し、賃金は定年退職前の60%程度とする契約が一般的です。
ところが、労働契約法第20条は「有期雇用契約社員と正社員との合理性なき賃金格差」を禁止しており、この禁止規定は再雇用制度における有期雇用契約にも適用されます。例えば2018年6月に下された「長澤運輸事件」判決では、年収が正社員時の79%なら合法としています。したがって現在、再雇用社員の賃金相場といわれている退職前の60%程度には注意が必要です。相場説を安易に踏襲する前に、賃金設定は自社の顧問弁護士や社会保険労務士と相談するのが無難です。
●合理的理由なき手当不支給は違法
再雇用社員に対する皆勤・精勤手当、住宅手当、通勤手当などの合理的理由なき不支給も違法とされています。
・再雇用の業務
再雇用社員に対し、定年退職前と異なる業務に従事させること自体は合法です。しかし、例えば定年退職前に営業職だった社員を再雇用後は清掃業務に従事させるなど、退職前とまったく接点のなかった業務に従事させると、裁判所から違法と判断される可能性が高いので注意が必要です。
・5年ルールへの対応
再雇用期間の設定において注意すべきなのが、労働契約法の「5年ルール」です。5年ルールとは、1年契約の有期雇用の契約を通算5年以上繰り返し更新した場合、社員が希望すれば、企業はその社員との雇用契約を無期の雇用契約に変更しなければならない法規制のことです。
したがって、「有能な人材なので5年を過ぎても再雇用を維持したい」場合は、再雇用制度とは別の雇用契約を改めて結ぶ必要があります。
再雇用契約書のテンプレート
再雇用制度を導入する際、人事担当者は次のような事項をチェックした上で制度設計を図る必要があります。
●改正高年齢者雇用安定法の法規制を正しく理解しているか
●自社の就業規則や賃金規定と再雇用制度との整合性はあるか
●再雇用予定者に提示する労働条件と再雇用制度との整合性はあるか
●再雇用契約期間の設定と5年ルールとの整合性はあるか
これらの事項をチェックした上で、人事担当者はシニア社員の経験と能力を存分に活用できる制度を設計し、「シニア社員をお荷物にしない」人事制度を指向するのが重要です。
そのためにも、再雇用契約書の書式は専門家テンプレートを活用すると良いでしょう。再雇用制度導入における人事担当者の役割は重大です。
再雇用契約書 無料ダウンロードはこちらから!
※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。
おすすめコンテンツ
人気記事ランキング
キャリア記事ランキング
新着動画
関連情報
-
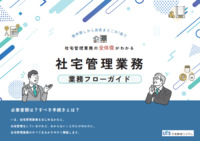
社宅管理業務の全体像がわかる!社宅管理業務フローガイド
おすすめ資料 -

令和7年度 税制改正のポイント
おすすめ資料 -

債権管理・入金消込効率化『V-ONEクラウド』導入事例 ~午前中いっぱい掛かっていた消込作業がわずか数分で完了! アデコ株式会社~
おすすめ資料 -

【新卒採用トレンド】優秀な人事は押さえている!新卒採用3大トレンド
おすすめ資料 -

人的資本開示の動向と対策
おすすめ資料 -

外部EAPとは?内部との違いや導入メリット、注意点を紹介
ニュース -

10~20代の「心の病」が最多を更新|企業が今すぐ取り組むべきメンタルヘルス対策とは
ニュース -

バーンアウトの構造と「燃え尽き」を防ぐワーク・エンゲージメント
ニュース -

テクノロジーハラスメントとは|IT化の裏で進む“静かな嫌がらせ”が増加する危険性
ニュース -
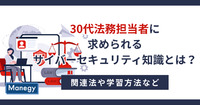
30代法務担当者に求められるサイバーセキュリティ知識とは?関連法や学習方法など(前編)
ニュース -

郵便物の電子化による部署別 業務効率化事例
おすすめ資料 -
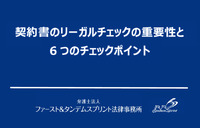
契約書のリーガルチェックの重要性と6つのチェックポイント
おすすめ資料 -

新型コロナウィルス問題と見直しておきたい契約条項
おすすめ資料 -
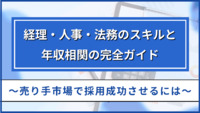
経理・人事・法務のスキルと年収相関の完全ガイド【MS-Japan】
おすすめ資料 -
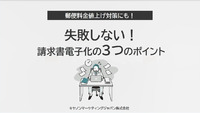
【郵便料金値上げ対策にも!】失敗しない!請求書電子化の3つのポイント
おすすめ資料 -
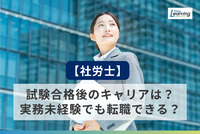
【社労士】試験合格後のキャリアは?実務未経験でも転職できる?
ニュース -
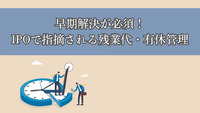
早期解決が必須!IPOで指摘される残業代・有休管理
ニュース -

「定性評価」をうまく取り入れて、組織や個人の能力を最大限に引き出す方法
ニュース -
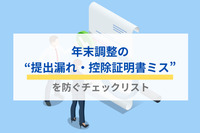
年末調整の“提出漏れ・控除証明書ミス”を防ぐチェックリスト
ニュース -
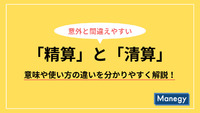
意外と間違えやすい「精算」と「清算」|意味や使い方の違いを分かりやすく解説!
ニュース






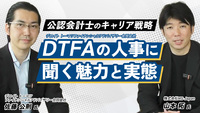















 ポイントをGETしました
ポイントをGETしました


