公開日 /-create_datetime-/
健康情報管理規程とは?9つの策定内容についてわかりやすく解説

健康情報管理規程は、働き方改革において義務付けられた取扱規程です。
近年、ストレスチェック制度が導入されたり、産業医の面接指導が強化されたりと、従業員の健康情報が増加傾向にあります。全事業者は、社員が心身ともに健康な状態で仕事ができるように、健康情報管理規程を策定する義務があります。
そこで今回は、健康情報管理規程の基礎を学びながら、どのような内容を策定すべきか、定められている9つのポイントについて解説をします。
目次【本記事の内容】
健康情報取扱規程とは
健康情報管理規程とは、従業員の健康情報を企業が取得・管理する方法について定めた規程です。
2019年4月、働き方改革法の施行によって、労働安全衛生法が改正されました。労働安全衛生法104条第3項では、企業が講じるべき健康情報保護措置として、「労働者の心身の状態に関する情報の適正な取扱いのために事業者が講ずべき措置に関する指針」の策定が義務付けられています。
これを健康情報管理規程といいます。情報の取り扱い方について、以下の点が定められています。
・労働者の心身の状態に関する情報を収集し、保管し、又は使用するに当たっては、労働者の健康の確保に必要な範囲内で労働者の心身の状態に関する情報を収集し、並びに当該収集の目的の範囲内でこれを保管し、及び使用しなければなりません。
・労働者の心身の状態に関する情報を適正に管理するために必要な措置を講じなければなりません。
(引用:改正労働安全衛生法のポイント|厚生労働省東京労働局)
労働者の心身の状態に関する情報とは健康診断やストレスチェックの結果、さらに産業医面談の記録のことです。これは「要配慮個人情報」と呼ばれています。
これを従業員と企業の人事、産業保健スタッフ(産業医・保健師)との三者間で取り扱うために健康情報管理規程を策定しなければなりません。
健康情報取扱規程の対象
健康情報管理規程を策定しなければならない対象は、全事業者です。これに違反した場合、労働基準監督署による行政指導の対象となります。
悪質な違反があった場合は、罰則が課されることもあるので、対策ができていない企業は早急に手を打つ必要があるでしょう。
健康情報管理規程がない場合、気づかない内に違反行為を犯かすことになるかもしれません。
例えば、以下のようなケースが該当します。
・健康診断やストレスチェックの実施を外部業者に委託
・就業上の相談をする場合、従業員の同意なく産業医面談の記録を上長に提供
・健康情報を取り扱う者が不在
・健康情報を本社・支社・営業所・グループ会社などの間で郵送
重度のストレスを抱えていると従業員が診断されても、そのまま社内で共有してしまうと、不利益が生じたり、誤解を招いたりするリスクがあります。
要配慮個人情報の取り扱いには守秘義務が肝心です。目的に沿って必要最低限の情報を使用しなければなりません。
健康情報取扱規程で策定すべき内容
健康情報取扱規程を作成するために、もっとも重視すべきは従業員の意見を取り入れることです。その上策定すべき内容には、以下の9点があります。自社の状況に合わせて詳細を取り決めていきます。
1.心身の状態の情報を取り扱う目的及び取扱方法
ここでの目的とは、従業員の健康確保措置の実施、または企業が負う民事上の安全配慮義務の履行が該当します。取扱方法とは、健康診断やストレスチェックの結果、長時間労働者等に対する医師による面接指導のことです。
2.心身の状態の情報を取り扱う者及びその権限並びに取り扱う心身の状態の情報の範囲
直接の権限を持つ監督的地位にある者、産業保健業務従事者及び管理監督者など、誰にどんな権限を与えて、どこまでの情報を開示するかを決定します。
3.心身の状態の情報を取り扱う目的等の通知方法及び本人同意の取得方法
通知および本人同意を取得する方法を決めます。従業員が承諾する意思表示には、書面でサインをもらう方法が合理的でかつ有効です。
4.心身の状態の情報の適正管理の方法
情報漏洩リスクを回避するために管理方法を定めます。例えば、パスワードがかかったサーバーで情報を管理したり、特定の健康情報管理責任者を選任したりする方法があります。」
5.心身の状態の情報の開示、訂正等(追加及び削除を含む。以下同じ。)及び使用停止等(消去及び第三者への提供の停止を含 む。以下同じ。)の方法
情報の開示請求があった場合、従業員から訂正・追加・削除の依頼があった場合、また使用停止の請求があった場合に、それぞれの対応方法を定めます。
6.心身の状態の情報の第三者提供の方法
第三者に情報提供をするか、しないのかを決めます。情報提供する場合、その方法についても明記します。
7.事業承継、組織変更に伴う心身の状態の情報の引継ぎに関する事項
合併や分社化、事業譲渡など事業承継によって健康情報等を取得する場合、どのように情報を引き継ぐのか定めます。
8.心身の状態の情報の取扱いに関する苦情の処理
健康情報の取扱いについての苦情を受けつける窓口(メールもしくは電話)を設けます。その後の適切な処理方法についても定めます。
9.取扱規程の労働者への周知の方法
社内メールへの掲載や社内研修の実施など、取扱規定を従業員に広く周知する方法について定めます。
まとめ
健康情報管理規程の基礎と、策定すべき9つの内容を解説しました。
なお、50人以上の労働者を常に雇用する場合は、衛生委員会を必ず設置しなければなりません。衛生委員会がある企業では労使や産業医とともに、月に1回以上の会議を開催する必要があります。
衛生委員会がある企業でも、ない企業でも健康情報管理規程は、経営者が一方的に決めるのではなく、従業員の意見に耳を傾けることを忘れてはなりません。また策定して終わりではなく、社員全体に周知していくことを徹底しましょう。従業員の健康管理に注力をすることは、これからの経営において重要なテーマになるでしょう。
※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。
おすすめコンテンツ
新着おすすめセミナー
人気記事ランキング
キャリア記事ランキング
新着動画
関連情報
-

上場企業・IPO準備企業必見!! 内部統制・監査の妨げになるアナログな入金消込とは
おすすめ資料 -

工事請負契約書とは?作成時の注意点などを解説!
おすすめ資料 -

業務委託契約書の書き方のポイントは?知っておくべき基礎知識
おすすめ資料 -

管理部門職種別 面接質問集【MS-Japan】
おすすめ資料 -

家賃補助と社宅・社員寮、自社に最適な住宅補助制度の選び方
おすすめ資料 -

新型コロナ破たん、1月は一転して150件割れ
ニュース -

旬刊『経理情報』2026年2月10日号(通巻No.1767)情報ダイジェスト②/会計
ニュース -

棚卸評価損の仕訳とは?計算方法・仕訳例・評価方法をわかりやすく解説
ニュース -
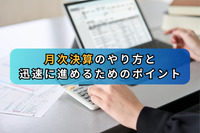
月次決算のやり方と迅速に進めるためのポイント
ニュース -

2026年1月の「人手不足」倒産 36件 春闘前に「賃上げ疲れ」、「人件費高騰」が3.1倍増
ニュース -

ハイブリッドワーク・ フリーアドレス導入に際して発生する課題は?
おすすめ資料 -

契約不適合責任とは?売買契約書で 注意すべきポイントについて
おすすめ資料 -

顧問契約書/コンサルティング契約書の作成で気を付けておくべき事
おすすめ資料 -

業務委託契約の基本がわかるハンドブック
おすすめ資料 -

社員と会社の両方が幸せになる生活サポートとは?
おすすめ資料 -

軽減税率導入で複雑化する請求書の消費税処理、経理担当者の手間を軽減するには?
ニュース -

【開催直前】『ManegyランスタWEEK -2026 Winter-』全セッションをまとめてチェック!
ニュース -

1月30日~2月5日のManegy人気記事ランキング|Weekly Ranking TOP10
ニュース -

収入印紙の消印とは?正しい押し方・使える印鑑・注意点をわかりやすく解説
ニュース -
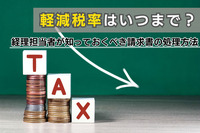
軽減税率はいつまで?経理担当者が知っておくべき請求書の処理方法
ニュース




































