公開日 /-create_datetime-/
人事労務の業務効率化するホワイトペーパーを無料プレゼント
チェックしておきたい法令関連の情報やノウハウやヒントなど業務に役立つ情報をわかりやすくまとめた資料をご紹介します。全て無料でダウンロード可能ですので、是非ご活用ください。
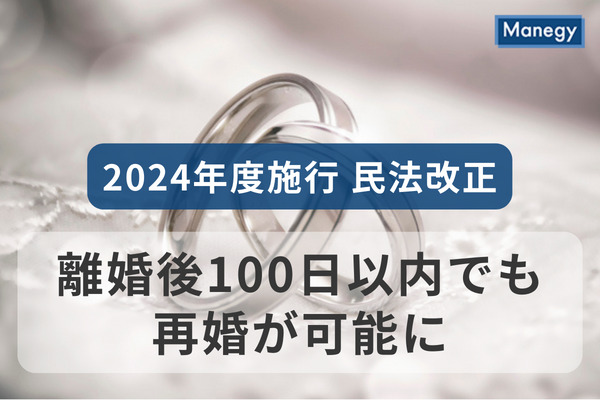
2024年に施行される民法改により、4月1日から、女性の再婚禁止期間が廃止されます。民法は婚姻や離婚など、プライベートな面とも深く関わる法律です。今年の改正内容は家族のあり方に深く関わる重大なものなので、ぜひ内容を把握しておきたいところです。
目次【本記事の内容】
そもそも民法とは、私人の間の権利や義務に関わる法律です。ここでいう私人とは、国・行政機関以外の個人や団体を差し、一般市民のほか企業・事業者も含みます。
たとえば、企業がビジネスの場で取り交わす契約などは、民法において規定されています。もし契約違反を犯した場合は、民法の規定に基づいて履行請求や損害賠償の請求が行われることになります。
民法は全5編で構成されています。第1編が「総則」、第2編が「物権」、第3編が「債権」、第4編が「親族」、第5編が「相続」です。企業の法務担当であれば、第3編の「債権」内にある「契約」に関わる箇所は、特に関わりの強い分野となるので、理解を深めておきましょう。
2024年に改正される民法は、ビジネスの場というより、家族関係に関わる内容です。具体的には第4編の「親族」に含まれている「再婚禁止期間」の廃止です。
コンプライアンスも扱う法務が業務に活かせる資料はこちら(無料)
従来の民法では、離婚後に再婚する場合、男性であればすぐに再婚が可能です。たとえば離婚した翌日に再婚をしても、法律違反にはなりません。
しかし女性の場合、再婚禁止期間が規定されています。民法においては、離婚してから100日を経過しないと、再婚はできないとされており、男女間において、ルールに違いがあります。
このような制度が定められているのには、同じく民法で規定されている「嫡出推定」に関わる内容と関係しています。嫡出推定とは婚姻中に妊娠した子を、法律上「婚姻中の夫の子」と認めることです。
現行の民法においては、離婚をした日から300日以内に出生した子は「前夫の子」と自動的に推定されます。たとえば妊娠中に離婚して、その後再婚した場合、離婚後に300日以内に出産したのであれば、生まれた子は「現在の夫」ではなく「前の夫」の子になるわけです。そうなると前の夫側の対応次第では、離婚後に親権をめぐる争いが発生し、最終的に子が前夫のもとに連れて行かれる可能性もあります。
人間の妊娠期間は、日数にして266~280日間ほどです。「100日を経過しないと結婚できない」との規定を設けることで、「前の夫と現在の夫、どちらの子なのか」といった混乱を防ごうとしたわけです。
なお、この100日ルールには例外が設けられ、以下のケースに該当する場合は離婚後100日以内の再婚も認められています。
・離婚する前から妊娠していた子を出産してから再婚する場合
・夫が3年以上生死不明で、それを理由とした離婚判決を経て、再婚する場合
・夫が失踪を宣告し、それにより婚姻が解消した後に再婚する場合
・離婚した夫と再婚する場合
・女性が受胎能力のない年齢である場合
この再婚禁止期間の規定が、2024年4月1日から完全になくなります。
もともと再婚禁止期間の規定は、明治憲法で定められていたものをそのまま用いたものです。当時は、医学が未発達だったため、父親の推定が重ならないように再婚禁止期間を設けていました。しかし、現代ではDNA鑑定によって、子どもの父親を特定することが可能となるため、再婚禁止期間が不要となるのです。
また、制度廃止に至った重要な背景は、子どもの無戸籍防止のためです。 再婚禁止期間が設けられていると、離婚後100日の間に出産した場合、戸籍上は自動的に前夫の子どもと記載されます。それを避けるため、あえて出生届を出さない母親も少なくありません。この場合、子どもは無戸籍になってしまいます。
出生届をしないで無戸籍になってしまうと、公的医療保険はもちろん、義務教育も受けられません。身分保証書の提示もできず、運転免許証、パスポートの取得もできなくなります。実は、こうした「前の夫の子と認定されたくない」との理由で出生届を出さなかった人は、法務省が把握しているだけでも、全国で581人に上っています(2022年時点)。これは、無国籍者の7割以上がこの理由に該当します。
今回の民法改正などでは、離婚から300日以内に生まれた子どもでも、法律上は前夫ではなく現夫の子と推定するとの規定も新たに設けられています。この改正法により、「離婚してすぐに再婚して出産したが、生まれた子が前の夫の子になることだけは避けたい」との理由で出生届を出さなかった人も、2024年度からは安心して届け出を出せるようになります。無戸籍の子どもをなくすという点で、改正法は一定の効果が期待できそうです。
コンプライアンスも扱う法務が業務に活かせる資料はこちら(無料)
今回紹介した再婚禁止期間の廃止により、無国籍の子どもの数が減少することを期待したいところです。
管理部門においては、法務担当者よりも従業員の労務データを管理する人事総務部門の方が間接的に関連することになりそうですので、改正の動きを押さえておきましょう。
万が一、離婚をする場合、自分の子どもを守るためにも、再婚に関する民法のあり方について事前に理解しておきましょう。
■参考サイト
【社労士監修】2024年4月労働基準法施行規則改正について
仕事と家庭の両立実現に向けて、2025年4月施行の育児・介護休業法等改正のポイント
※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。

総務・経理・営業の生産性に影響する法人車両の駐車場管理における落とし穴

【離職率を改善】タレントマネジメントシステムの効果的な使い方

健康経営の第一歩! 健診受診率100%を達成するコツ一覧

顧問契約書/コンサルティング契約書の作成で気を付けておくべき事

フランチャイズ契約を締結する前にチェックすべきポイントとは(加盟店の立場から)

研究開発費及びソフトウェアの会計処理 第4回 ソフトウェアの導入費用の取扱い
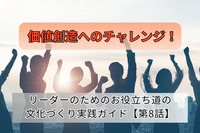
価値創造へのチャレンジ!/リーダーのためのお役立ち道の文化づくり実践ガイド【第8話】

管理部門の今を知る一問一答!『働き方と学習に関するアンケート Vol.3』
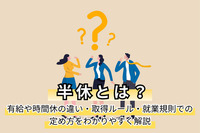
半休とは?有給や時間休の違い・取得ルール・就業規則での定め方をわかりやすく解説

「円安」倒産 1月では10年間で最多の6件 43カ月連続で発生、負債は11倍に大幅増

今からでも間に合う! 中小企業にお勧めな電子帳簿保存対応

業務委託契約書の書き方のポイントは?知っておくべき基礎知識

シニア雇用時代の健康管理の備えとは? 健康管理見直しどきナビ

フリーアドレスの成功事例 ご紹介
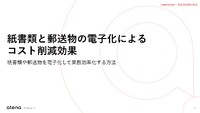
紙書類と郵送物の電子化によるコスト削減効果
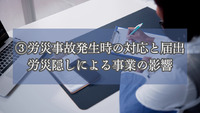
③労災事故発生時の対応と届出│労災隠しによる事業の影響
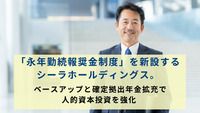
「永年勤続報奨金制度」を新設するシーラホールディングス。ベースアップと確定拠出年金拡充で人的資本投資を強化

法務の転職は「コンプライアンス経験」が武器になる!履歴書・職務経歴書でのアピール方法と成功事例(前編)

『不調になってから』では遅い Smart相談室が描く、個人と組織の成長が一致する職場のつくり方
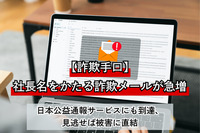
【詐欺手口】社長名をかたる詐欺メールが急増 日本公益通報サービスにも到達、見逃せば被害に直結
公開日 /-create_datetime-/