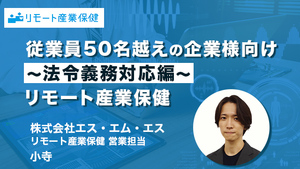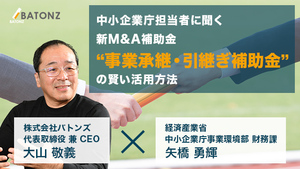公開日 /-create_datetime-/
【社会保険労務士執筆】健康保険・厚生年金保険(令和6年10月1日施行)の適用拡大における企業担当者向け実務のポイント
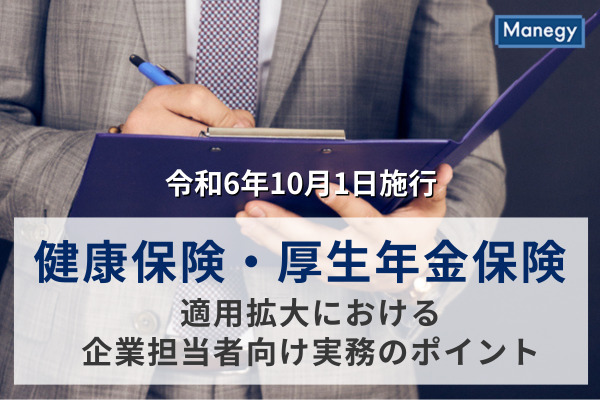
目次本記事の内容

この記事の筆者
上見 知也
イデアル社会保険労務士事務所
社会保険労務士
IT業界に10年間身を置き、Webサイトの制作者としてチームリーダー等を経験。社労士試験合格後、社会保険労務士法人、一般企業の人事・労務部門での勤務を経て、2023年に独立開業。
主に中小企業の人事労務面のサポートを行っている。
なぜ健康保険・厚生年金保険の適用拡大が必要だったのか
「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大Q&A集(令和6年10月施行分)」には、下記の通り回答されています。
政府においては、これまでも法律改正を通じて、短時間労働者に対する厚生年金保険・健康保険の適用拡大(以下「適用拡大」という)の取り組みを進めてきており、その意義については、以下の点があるとされています。
①被用者でありながら国民年金・国民健康保険加入となっている者に対して、被用者による支えあいの仕組みである厚生年金保険や健康保険による保障を確保することで、被用者にふさわしい保障を実現すること。
②労働者の働き方や企業による雇い方の選択において、社会保険制度における取扱いによって選択を歪められたり、不公平を生じたりすることがないようにすること等により、働き方や雇用の選択を歪めない制度を構築すること。
③適用拡大によって厚生年金保険の適用対象となった者が、定額の基礎年金に加えて報酬比例給付による保障を受けられるようになること等を通じて、社会保障の機能を強化すること。
lockこの記事は会員限定記事です(残り4811文字)
会員の方はログインして続きをお読みいただけます。新規登録するとManegy内で使える1,600ポイントをプレゼント!またログインして記事を読んだり、アンケートに応えたりするとポイントが貯まって、豪華景品と交換できます!
おすすめコンテンツ
人気記事ランキング
キャリア記事ランキング
新着動画
関連情報
-
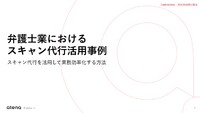
弁護士業におけるスキャン代行活用事例
おすすめ資料 -

債権管理・入金消込効率化『Victory-ONE/G4』導入事例 ~自動消込照合率が91%まで上昇! 株式会社有隣堂~
おすすめ資料 -

~質の高い母集団形成と採用活動改善へ~内定辞退者ネットワークサービス資料
おすすめ資料 -
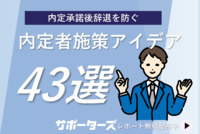
【内定者フォロー施策】内定承諾後辞退を防ぐ 内定者フォロー施策アイデア43選
おすすめ資料 -

業務委託契約の基本がわかるハンドブック
おすすめ資料 -

人事制度設計とは|設計の流れや注意すべきポイントを解説します
ニュース -

法人携帯のMNP(乗り換え)方法まとめ|費用や注意点も
ニュース -

退職代行とは?メリットやデメリット、具体的な取り組み事例やポイントを紹介
ニュース -

見積書に有効期限は必須!その理由や業界・状況別の決め方を詳細解説
ニュース -

経理の仕事はきつい?3つの解決策や向いている人・向いていない人の特徴など
ニュース -

OFFICE DE YASAI 導入事例
おすすめ資料 -

サーベイツールを徹底比較!
おすすめ資料 -
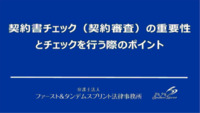
契約書チェック(契約審査)の重要性とチェックを行う際のポイント
おすすめ資料 -

【電子署名の導入を検討中の方にオススメ!】電子署名ガイドブック
おすすめ資料 -

英文契約書のリーガルチェックについて
おすすめ資料 -
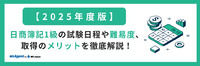
日商簿記1級の試験日程や難易度、取得のメリットを徹底解説!
ニュース -
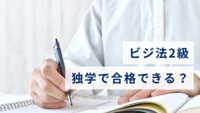
【2025年版】ビジネス実務法務検定2級(ビジ法2級)とは? 概要や独学で合格する勉強法を徹底解説!
ニュース -
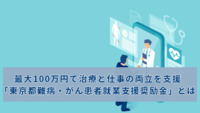
最大100万円で治療と仕事の両立を支援「東京都難病・がん患者就業支援奨励金」とは
ニュース -

【BCP対策の新常識】クラウドバックアップで実現するコスト削減
ニュース -
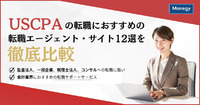
【7月最新版】USCPAにオススメの転職エージェント・サイト12選を徹底比較!
ニュース










 ポイントをGETしました
ポイントをGETしました