公開日 /-create_datetime-/
経理財務限定!業務に役立つ資料を無料プレゼント
業務過多や属人化などの課題を解決する資料から経費精算の効率化など業務に役立つ資料をプレゼント。また法令関係など正しく理解しておきたい方に向けた資料もご用意しております。すべて無料でダウンロードできます。
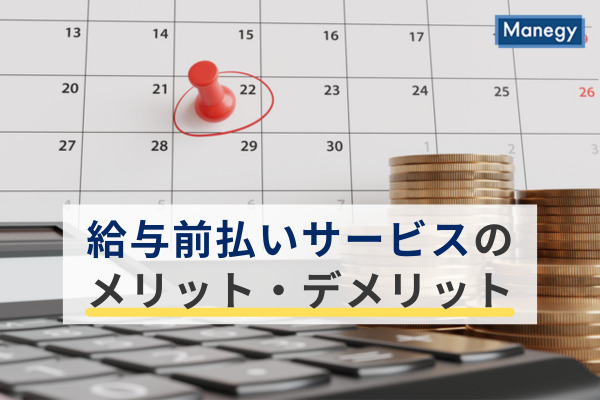
近年注目を集めている福利厚生の1つが「給与の前払い制度」です。働いた分の給与の一部を給料日前に受け取れるため、生活の大きな助けになります。 制度の導入に際しては、サービス会社を活用するのが一般的です。
この記事では給与前払い制度の概要や、サービス会社を利用するメリットとデメリットなどについて解説します。
給与前払いとは、働いた分の給与を給料日より前に受け取れる制度で、福利厚生として導入されることがあります。
たとえば給与システムが月末締めの翌月25日支払いだった場合、9月の労働分の給与は10月25日に振り込まれるのが通常です。
給与前払いシステムを利用すれば、10月1日から10月24日の間に9月分の給与が支給されます。受け取れる金額の上限や、支給可能日などは企業によって異なります。 物価高や貯蓄額の減少に対応する策として、導入する企業が増えているようです。
企業が給与前払い制度を導入する場合、自社の経理だけで処理するよりも、他社が提供する有償の給与前払いサービスを利用する方が一般的です。多くの場合、従業員が利用金額に応じて各種の手数料を負担する形で、利用料を支払います。
給与前払いサービスでは主に「立替払い」と「自社払い」の2つの仕組みがあります。それぞれ解説します。
サービス会社が前払い分の給与を、企業にかわって振り込む方式が「立替払い」です。メリットは、企業があらかじめ前払い分の給与を用意する必要がないことです。一方で、従業員や会社が負担する手数料は高くなる傾向にあります。
企業側が前払い給与に充てる資金を用意し、サービス会社が振込などの諸手続きを代行する方式が「自社払い」です。
企業はサービスの導入において初期費用がかかりますが、手数料は減少する傾向にあります。
給与の支払いに関しては、各種保険料の控除や法的問題への対応も必要です。そのため、導入の際には事前に、きちんとした制度を確立しなければなりません。
そこで、給与前払いサービスの導入方法や利用の流れについて解説します。
まずは前払い制度を導入する企業が、サービス会社へ利用の申し込みを行います。サービス会社は財務状況などを審査し、利用の可否を判断します。
審査に通ればサービス導入に向けた準備です。従業員への説明や経理システムとの連携、従業員へのシステムアカウントの発行などを行います。
すべての準備が整えば、サービスが利用できるようになります。一般的な利用の流れは以下の通りです。
①従業員による前払いの申請
②所属企業またはサービス会社からの振込
③給与日に差額の支払い
④立替払いの場合は企業からサービス会社へ利用分の支払い
利用の流れや支払いタイミングなどはサービス会社によって異なるため、事前にご確認ください。
給与前払い制度の導入および、サービス会社の利用にはメリットもデメリットもあります。いずれも理解した上で、導入を検討しましょう。
まず、制度の導入自体のメリットは「採用活動が有利になること」と「従業員の定着率の増加」です。物価上昇の影響などで、短いスパンでの給与の受取を希望している人は決して少なくありません。そういった方にとって、給与の前払い制度は非常に魅力的でしょう。 また、サービス会社を利用することで、企業の振込業務などを削減でき、制度の導入における企業の負担を減らせます。
給与の前払い制度の導入におけるデメリットは、なんといってもコストの増加です。従業員が負担する手数料や、企業が負担する運用コストなどがかかります。
また、ほとんどの作業をサービス会社が代行してくれるとはいえ、導入や運用に手間もかかります。
費用や手間に見合った福利厚生なのかを慎重に検討しましょう。
給与の前払いのサービス会社を選ぶポイントは「費用や手数料」と「使い勝手」の2点です。それぞれ解説します。
費用や手数料など、いわゆるコストはサービス会社を選ぶ上で非常に重要な要素です。そもそも前払いを利用したい従業員は金銭的に余裕がない場合がほとんどです。
システムの利用手数料がかさんで総合的な手取りが減ってしまえば、従業員の生活を圧迫してしまうおそれもあります。
従業員と企業はそれぞれ、最終的にどれくらいのコストがかかるのか、事前に把握しておきましょう。
前払い申請をする上で、使い勝手は非常に重要です。「従業員が口座を持っている銀行と連携しているのか」「アプリなどで手軽に申請できるのか」などを事前に確認するとよいでしょう。
物価上昇や貯蓄額の減少などを理由に、給与の前払い制度が福利厚生として大きな注目を集めています。導入の際には、サービス会社を利用することで会社の業務負担を抑えられるでしょう。
一方で、サービス会社を利用すれば手数料や運用費用などのコストがかかります。費用に見合ったサービスかどうかを慎重に検討して導入を進めましょう。
【参考】給与前払いのサービス一覧※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。

【1on1ミーティング】効果的な実践方法と運用時のポイント

債権管理・入金消込効率化『Victory-ONE/G4』導入事例 ~入金消込の効率が飛躍的にアップ! ティーペック株式会社~

採用力・定着率を強化し、法定福利費も削減。 "福利厚生社宅"の戦略的導入法を解説

クラウド郵便の活用事例 - リモートワークだけじゃない!様々な課題に併せたクラウド郵便サービスの使い方-

債権管理・入金消込効率化『Victory-ONE/G4』導入事例 ~30時間かかっていた入金消込がほんの数十秒に! 伊藤忠エネクス株式会社~

社内飲み会「参加したい」6割超、希望場所はオフィス ケータリング急増で「会議室の花見化」進む

政策金利上昇で「自動昇給」、0.25%増で月1.25万円の給料アップ 住宅ローン会社が導入

賃上げ実施も9割超が「生活改善せず」と回答 従業員の8割が望む「第3の賃上げ」の実態を調査

6割の総務が福利厚生と従業員ニーズのギャップを実感するも、3割超が見直し未実施
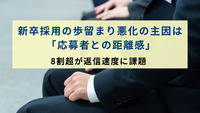
新卒採用の歩留まり悪化の主因は「応募者との距離感」 8割超が返信速度に課題

【新卒採用トレンド】優秀な人事は押さえている!新卒採用3大トレンド

英文契約書のリーガルチェックについて

業務委託契約の基本がわかるハンドブック

業務委託契約書の書き方のポイントは?知っておくべき基礎知識

債権管理・入金消込効率化『V-ONEクラウド』導入事例 ~午前中いっぱい掛かっていた消込作業がわずか数分で完了! アデコ株式会社~
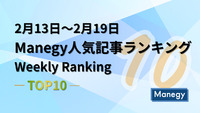
2月13日~2月19日のManegy人気記事ランキング|Weekly Ranking TOP10

平均10.4%賃上げ、初任給30万円へ 荏原実業が中計とKPIで描く、「戦略的」人的資本経営
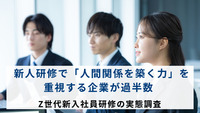
新人研修で「人間関係を築く力」を重視する企業が過半数 Z世代新入社員研修の実態調査

冬のボーナス支給、物価高の影響色濃く 日本インフォメーション調査
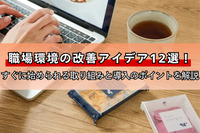
職場環境の改善アイデア12選!すぐに始められる取り組みと導入のポイントを解説
公開日 /-create_datetime-/