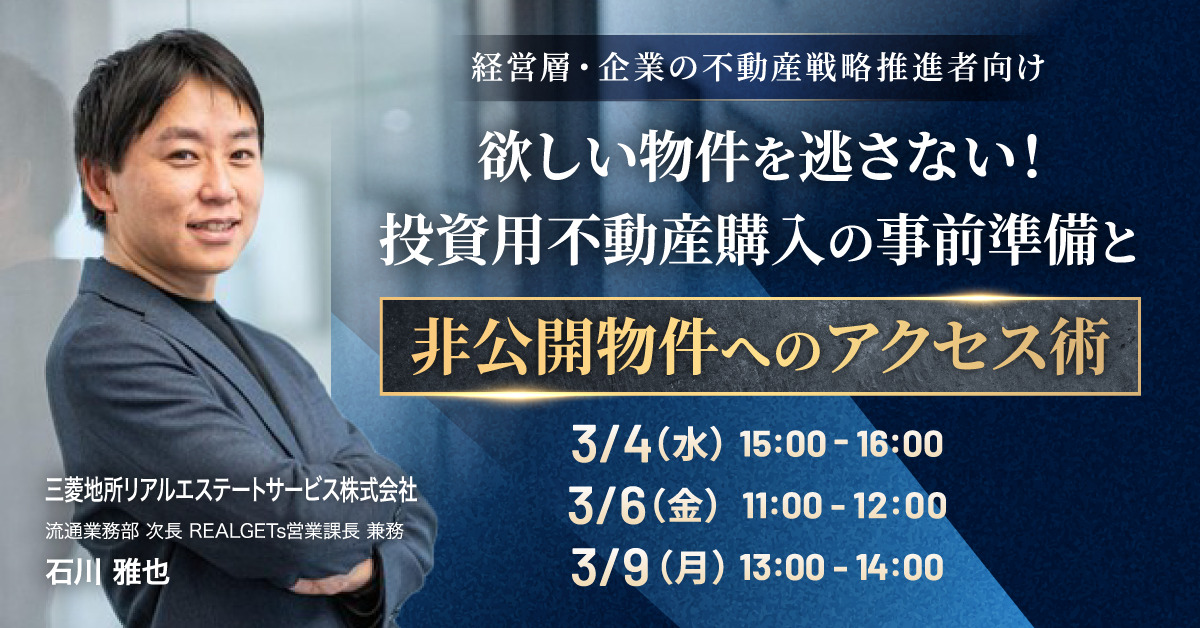公開日 /-create_datetime-/

テレビのニュースや新聞、経済雑誌などでよく取り上げられている指標の1つに「日経平均株価(日経平均)」があります。毎日のように目にし、耳にするワードではありますが、そもそも何かと尋ねられると、ビジネスパーソンであっても正確に答えられない方は多いのではないでしょうか。そこで今回は、日経平均株価とは何かを解説し、これまでの最高値と最低値、さらに過去最も大きかった上昇幅と下降幅について解説します。
目次【本記事の内容】
そもそも日経平均とはどんな指標かをおさらい
日経平均株価とは、日本経済新聞社が算出して公表している株価指数のことです。具体的には東証一部上場企業のうち、市場流動性の高い銘柄を中心に、業種のバランスに配慮して選出された225銘柄の平均株価のことを指します。株式市場の相場動向や景気判断の信用性の高い指標として利用され、日経平均の値動きに関連付けられた金融商品(先物取引や投資信託)も少なくありません。
なぜ225銘柄で計算されるのかについては、日本経済新聞社自身が「詳しい経緯は不明」としています(日本経済新聞社『よくあるご質問(日経平均株価について)』より)。すでに60年以上の歴史を持ち、算出・公表を開始した当時から225銘柄と定められていましたが、銘柄数自体に特別な意味はないというのが日本経済新聞社の見解です。売買高の多い銘柄を業種間のバランスを考慮して選んだところ、225になったのではないか、とも言われています。
なお、225はあくまで枠数なので、構成銘柄はずっと固定されているわけではありません。銘柄は年に1回行われる「定期見直し」と、上場廃止などに伴って銘柄を補う「臨時入れ替え」によって変わります。対象銘柄には「トヨタ自動車」や「日本電気」など日本を代表する企業が多く含まれていますが、近年では「ディー・エヌ・エー」(2015年に選定)や「楽天」(2016年に選定)などIT関連企業が選ばれるようになりました。
日経平均が一番高かった日とその金額は?
日経平均が史上最も高かったのは、バブル絶頂期だった1989年(平成元年)12月29日、その年最後の取引日である「大納会」の日です。その日の取引時間中の最高値は3万8,957円44銭、終値(その日最後の売買成立時の株価)は3万8,915円87銭でした。
当時は政府による積極財政政策(政府が社会資本整備のために積極的に財政支出を増やす政策)と日銀による低金利政策(企業が金融機関から低金利で融資を受けられるようにし、投資を促進させる政策)が、空前の好景気が起こっていました。いわゆる「バブル経済」と呼ばれる状況で、膨大な投資マネーが空前の財テクブームを引き起こし、株式投資、不動産投資が盛んに行われた時代です。1989年の1年間だけで株価は8750円35銭も上昇し、「1990年中に、日経平均は5万円に達する」との強気な見通しさえ当時はありました。
日経平均が一番低かった日とその金額は?
ところがご存じの通り、バブル経済は長く続きませんでした。4万円近くに達していた株価はその後1年あまりで約半値まで低下し、それに伴い不動産を始めとする資産価格も暴落します。それから約10年後の1999年~2000年にはヤフーなどIT関連企業の株が多量に買われ、いわゆる「ITバブル」が発生しましたが、ほどなく崩壊し、2003年の4月に日経平均は「7,607円」にまで下落しました。
そんな中、当時の小泉純一郎首相が郵政民営化をめぐる解散総選挙で圧勝し、規制緩和推進への期待感から再び株価が上昇します。2007年には1万8,000円を超える水準にまで達しました。
これもご存じかと思いますが、2008年にリーマンショック(アメリカの住宅価格が下落して「サブプライムローン」が不良債権化し、世界中の金融機関に多額の損失が発生)が起こります。これにより、日本経済も大打撃を受け、そのあおりにより日経平均は大きく低下し、2008年10月28日には一時「6,994円90銭」と7,000円を割り込み、バブル崩壊後の最安値を記録しました。終値としての最安値は、2009年3月10に記録した「7,054円98銭」です。
日経平均が一番上がった日と上昇幅は?
最も日経平均の上昇幅が大きかったのは、バブル経済が崩壊しつつあった1990年10月2日で、前日からの上昇幅は「2676円55銭」でした。同日の日経平均の終値は2万2,898円41銭で、先ほど紹介した通り1989年12月29日(大納会)時点では3万8,915円87銭でしたから、その時から1年も経たないうちに1万5,000円以上も下がっています。つまり、バブルが崩壊して株価が下がり続けている最中、その反発(株価が下落した日の翌日に株価が上昇すること)が起こった際に生じた株価上昇が、過去最高の上昇幅です。
日経平均が一番下がった日と下降幅は?
過去最大の下降幅が日経平均で起こったのは、世界同時株安が発生した「ブラックマンデー」の翌日、1987年10月20日です。前日から終値で「3,836円48銭」も下落し、2万1,910円となりました。
ブラックマンデーとは、1987年10月19日にダウ平均(「S&Pダウ・ジョーンズインデックス」が算出して公表しているアメリカを代表する株式指標)が1日で508ドル下落した事態のことを指します。下落率の大きさが世界恐慌の引き金となった1929年の「ブラックサーズデー」よりも大きかったこともあり、株価暴落の影響は世界中に飛び火しました。日本もそのあおりを受け、一時的に株価が大幅に下落したのです。しかし日本は当時、政府の金融緩和策によりバブル経済が起こっていたこともあり、影響は最小限にとどまりました
まとめ
日経平均の過去最高値と最安値、さらに最大の上昇幅と下降幅の歴史をみていくと、20世紀後半の日本経済さらには世界経済の変遷を理解できます。経済の動き読み取る上で、日経平均は重要な情報源であるわけです。これまで日経平均の変動にあまり関心がなかったという方は、これを機会に、日々の値動きに注目してみてはいかがでしょうか。
■参考サイト
ビジネスでもよく使われる「企業価値」について再認識しよう
日経平均史上最大の暴落はいつ? いまさら聞けない「日経平均株価」とは
あなたは答えられる? 株価が上がる理由・下がる理由
株価が下がるとどういう影響があるの?
※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。
おすすめコンテンツ
新着おすすめセミナー
人気記事ランキング
キャリア記事ランキング
新着動画
関連情報
-

社員と会社の両方が幸せになる生活サポートとは?
おすすめ資料 -

26卒エンジニア学生551名に聞く|志望度が上がる・下がるサマーインターンシップ調査レポート
おすすめ資料 -

労働契約と業務委託契約の違いとは?契約書に記載すべき重要ポイントを解説
おすすめ資料 -

【新卒採用トレンド】優秀な人事は押さえている!新卒採用3大トレンド
おすすめ資料 -

業務委託契約(Service Agreement)の英文契約書を作成する際の注意点を弁護士が解説
おすすめ資料 -

衆院選の争点 「内需拡大の推進」41.8%政党支持率は、大企業と中小企業で違いも
ニュース -

労基法大改正と「事業」概念の再考察 ~事業場単位適用の実務~
ニュース -

研究開発費及びソフトウェアの会計処理 第3回 自社利用のソフトウェアの定義と会計処理等(企業会計と税務会計の違い)
ニュース -

新聞図書費とは?経理が押さえておきたい対象経費と仕訳の基本
ニュース -

AIの反社チェック・コンプライアンスチェック 信じちゃダメです。本当に絶対ダメです。
ニュース -

新卒エンジニア採用施策アイデア大全
おすすめ資料 -

アフターコロナの採用戦略とコスト最適化
おすすめ資料 -

新型コロナウィルス問題と見直しておきたい契約条項
おすすめ資料 -

金融業界・製造業界 アルムナイネットワーク事例集
おすすめ資料 -

採用力・定着率を強化し、法定福利費も削減。 "福利厚生社宅"の戦略的導入法を解説
おすすめ資料 -

②労災事故発生時の対応と届出│労働者死傷病報告提出のタイミング~労働者死傷病報告の方法と内容
ニュース -

旬刊『経理情報』2026年2月20日号(通巻No.1768)情報ダイジェスト①/税務
ニュース -

採用計画で市場価値を上げる8つのスキル|戦略人事へのキャリアパスを徹底解説【転職成功事例つき】(前編)
ニュース -

フランチャイズ契約とは?ロイヤリティ・テリトリー・競業避止など契約条項を徹底解説
ニュース -
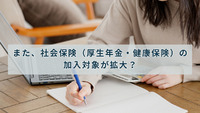
また、社会保険(厚生年金・健康保険)の加入対象が拡大?
ニュース